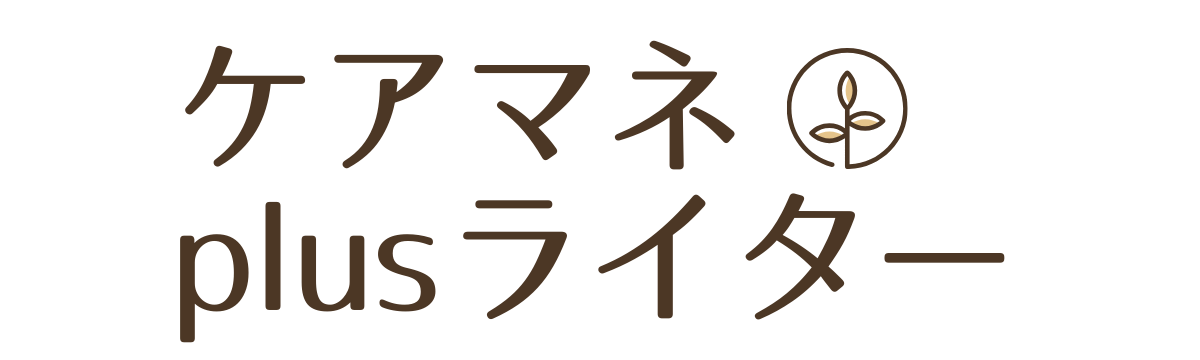皆さんの事業所では、支援経過の書き方に決まったルールはありますか?
多少のルールはあったとしても、書くボリュームはケアマネによってバラバラな事業所も多いのではないでしょうか。
私は居宅ケアマネになって14年、現在は主任ケアマネで管理者をしています。
これまで多くのケアマネさんと一緒に仕事をしてきた経験から言うと…
実は、この支援経過、書き方ひとつで残業時間にかなり影響を及ぼすものなのです。
今回は、日々の業務の中でも特に時間を取られがちな支援経過記録についてのお話をしたいと思います。
是非、ケアマネ歴1~2年の新人ケアマネさんに読んでほしい。
なぜなら、ケアマネ歴を重ねるほど、支援経過の書き方を変えるのが難しくなるからです。
私がそう思う理由や、効率的に支援経過を書く方法、記録するべき内容についてまとめます。
この記事を参考にして、ワーク・ライフ・バランスが充実しているケアマネを目指しましょう!
支援経過記録のボリュームが大きいケアマネは残業が多い

私の事業所は、支援経過の書き方に決まったルールはなく、ケアマネによってバラバラです。
理由は法人内の異動が多く、新人ケアマネのときに誰に教わったかによって違いがあるのだと思います。
異動してきたケアマネが、3か月分の支援経過を20ページにも及んで記録しているのには驚きました。
他にもデスクにいるほとんどの時間、キーボードを叩き続けているケアマネ。
どちらも主任ケアマネを取得しており、経験は十分に積んできた人達です。
私のこれまでの経験から、このようなケアマネさん達には以下のような共通点がありました。
- 不要なことまで書いている自覚がない
- 必要なことを書き忘れる
- 利用者の支援経過ではなく、自分の行動を記録している
- メモが苦手、忘れないように急いで支援経過に記録する
- 支援経過を優先し、期限付きの業務ができずに残業する
新人ケアマネ時代に、このような主任ケアマネの指導を受けると同じようになってしまうかもしれません。
何年もケアマネを続けていると支援経過の書き方に自分なりの型のようなものが定着してしまい、それを直すのが難しくなっていきます。
実は私自身も支援経過が長くなりがちな一人です。
自覚はあるので、”支援経過は簡潔に、詳細は後から思い出せるようにメモにキーワード” これを意識しています。
効率的な支援経過の書き方

では、どうすれば効率的に、かつ質の高い支援経過が書けるのでしょうか。
ポイントは以下の3つです。
5W1Hを意識した「事実ベース」の記録
5W1Hを意識して、明確に記録するとわかりやすいです。
- 誰が(Who)
- いつ(When)
- どこで(Where)
- 何を(What)
- なぜ(Why)
- どのように(How)
長文がダメで短文が良いというわけではありません。
誰が見てもわかりやすく、客観的に記録することを心がけましょう。
- NG例:○○さんが困っていたので病院に連絡した⇒「困っていた」は主観的
- OK例:〇月〇日、〇〇様より受電。「最近体調が優れず食欲もない」と相談があったため、主治医に状況を報告し受診を促した
効率的な支援経過は「書く前に整理」「型で書く」
伝えたいことは簡潔に、しかし具体的に記載することが大切です。
- 出来事(何があったのか)
- 対応(どうしたのか)
- 評価・次回への視点
支援経過の見出しやタイトルに、キーワードを入れると後で見返すときに探しやすくなります。
例えば「緊急入院」「サービス変更」「家族より〇〇の相談」など。
複数の情報を羅列する際は、箇条書きにするのもわかりやすいですね。
この流れを意識すると、短くても要点が伝わる記録になります。
日時:2025年7月30日 14時~14時20分
タイトル:モニタリング・通所リハ利用時間の相談
内容:利用者宅を訪問し本人と面談。※別紙モニタリング表を参照
- 整形外科受診後より鎮痛剤を服用しているが、右足の痛みが治まらず。
- 排泄など日常生活動作は痛みがありながらも可能。
- 本人より通所リハの利用には満足しているが、右足の痛みにより短時間の利用で様子をみたいと意向あり。(入浴支援要)
- 通所リハ事業所に短時間利用の可否を確認予定。不可の場合はベッド臥床などの対応を相談することで本人承諾。
所見:右足の痛みが継続しており、通所リハの利用について調整の必要あり。痛み増悪の場合は再受診が必要
支援経過にありがちな非効率な書き方
支援経過にありがちな非効率な書き方の一例です。
- サービス担当者とのやりとりをダラダラ書く⇒結論をベースに要点をまとめて書く
- 逐語録が多すぎる⇒利用者・家族の重要な発言のみ逐語録にする
- 上司への確認や報告したことまで書いている⇒不要
漠然と起こった出来事を羅列してしまうと、以下のような問題が生じ、結果として残業の原因になってしまいます。
- 必要な情報を見つけるのに時間がかかる
- 同じような内容を何度も記載して無駄な時間を費やす
- 運営指導前の確認作業に時間がかかる
【運営指導対策】支援経過に記録すること

支援経過には必要なことを書き、必要でないことは書かない。
これが効率的な支援経過の書き方ですが、運営指導を見据えて、必ず記録しなければならない内容があります
運営指導とは質の向上を図るために行政の担当者が介護事業所を訪問し、書類や現場を確認。通常は事業所の指定期間(6年)に1回以上行われる行政指導。
以下に、場面ごとに記録しなければならない内容をまとめておきます。
初回訪問~アセスメントのときに支援経過に記録すること
- 介護保険証・負担割合証の確認
- 介護支援専門員証の提示
- 契約書・重要事項説明書の説明・同意・交付
- 利用者宅でアセスメントを実施(※別紙アセスメント表を参照)
- 利用者に複数のサービス事業所を提案
サービス担当者会議のときに支援経過に記録すること
- サービス担当者会議の実施(※別紙サービス担当者会議の要点を参照)
- レンタルか購入か選択できる歩行器、歩行補助杖、スロープを利用者が希望の場合、メリット・デメリットを説明し、専門家の意見を得て検討(サービス担当者会議の要点でもOK)
- ケアプランにインフォーマルサービスを位置づけなかった場合の理由(サービス担当者会議の要点でもOK)
- 居宅サービス計画書1・2・3表を利用者に説明・同意・交付
- 居宅サービス計画書1・2・3表をサービス事業所に交付
- 居宅サービス計画書4表を(サービス担当者会議欠席の)サービス事業所に交付
- 居宅サービス計画書1・2・3表を主治医に交付(更新時と医療系サービス利用の場合)
- サービス事業所に個別援助計画の提出を依頼
- 軽微な変更と判断した場合の根拠
モニタリングのときに支援経過に記録すること
- 利用者宅を訪問し利用者と面談。モニタリング実施
- 居宅サービス計画書6・7表を利用者に説明・同意・交付
- 利用者宅でモニタリングができない場合、特段の事情に該当する根拠
その他の場面のときに支援経過に記録すること
- 各種加算算定時の根拠
- 入院時情報連携加算の場合は入院日時を記載
- 介護保険更新(区分変更)申請代行
- 認定調査実施
まとめ:目指せ!ワーク・ライフ・バランスのとれたケアマネ

支援経過の記録は、日々の業務の中で見過ごされがちですが、ケアマネ業務効率化には欠かせない要素です。
支援経過を書くボリュームが大きいケアマネは、かなりの確率で残業が増えます。
効率的に、かつ質の高い支援経過を書くには、新人ケアマネのうちから意識して身につけることが大切です。
それは経験を重ねるごとに、自己流の型が定着してしまい直せなくなるケアマネが多いからです。
ダラダラと書くのではなく、必要なこと・必要でないことを理解して記録していくことが、運営指導対策にも繋がっていきます。
運営指導では、記録がないとやっていないと見なされてしまうこともあります。
ボリュームのある支援経過だったとしても、必要な記録がないと悲しい結果になってしまうかもしれません。
新人のうちから意識して取り組み、ワーク・ライフ・バランスが充実しているケアマネを目指しましょう!
本記事に記載されているノウハウおよび手順は、筆者(主任介護支援専門員)の長年の実務経験と、特定の地域・事例における解釈に基づくものです。介護保険法、運営基準、地域の条例、および各保険者(市町村)の解釈は常に更新・変更される可能性があります。個別の判断や法的な解釈については、必ず所属法人の指導者、専門機関、または関係自治体にご確認のうえ、ご自身の責任においてご活用ください。
ステップアップを目指す方、運営指導って何するの?と思った方は、こちらの記事も参考にしてください。