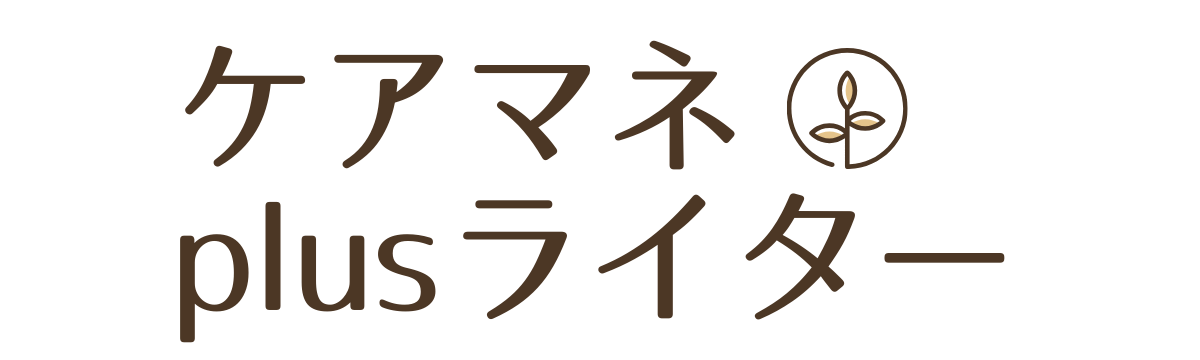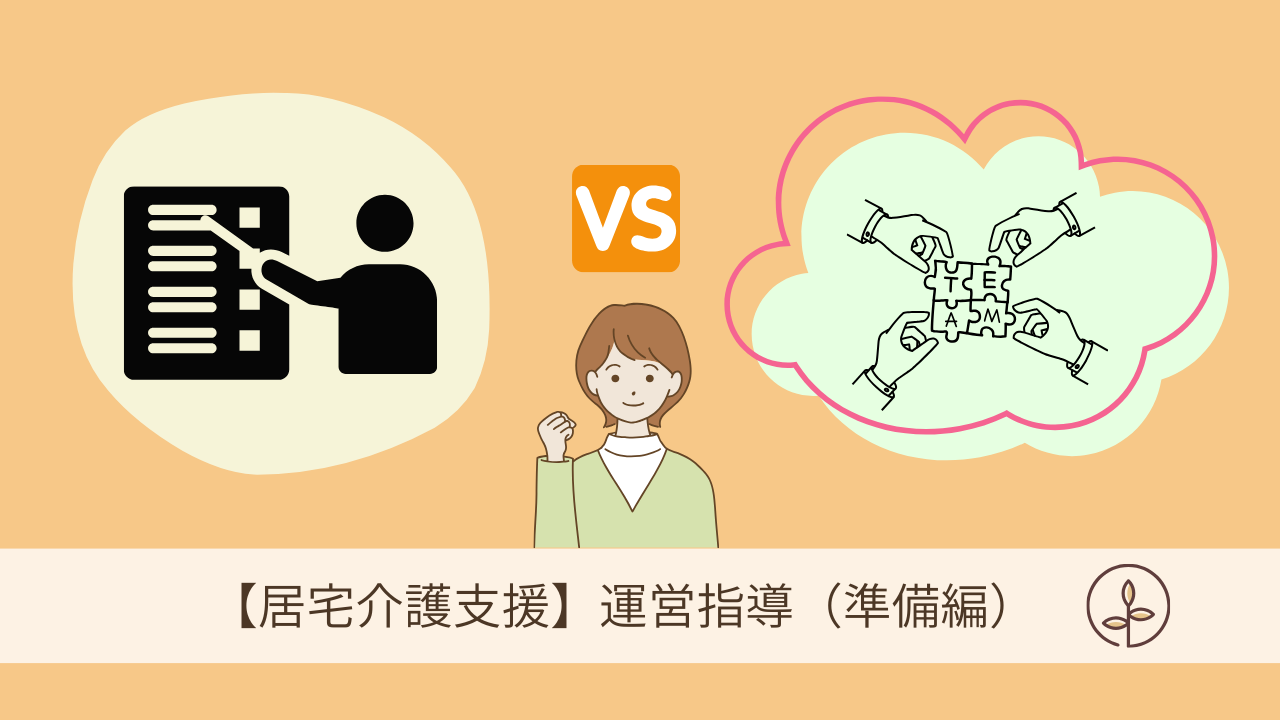その電話はある日突然かかってきました。
「○○市指導監査課です。貴事業所の運営指導を行うことになりました。来月の〇日か〇日でお願いします」

上司と相談して、明日明後日のうちにお返事させていただきます。
電話を切ってから、私が大急ぎで上司のもとに走ったのは言うまでもありません…
結論から言うと、居宅ケアマネ歴14年、今回が3回目の運営指導、問題なくクリアすることができました。
運営指導が決まってからの約1か月の苦労が報われた瞬間!
そこで今回は、運営指導に不安を感じている居宅介護支援事業所のケアマネさん向けに、私の事業所で行った準備計画の取り組みや、実際に運営指導で確認された内容についてまとめていきたいと思います。
まずは第一弾、運営指導【準備編】です。
しっかりと対策し、自信をもって運営指導に臨めるよう、是非、参考にしてください。
ただし、保険者によって注目するところに違いがあると思うので、そこはご理解の上、読んでください。
事前提出書類と当日の提出・提示書類
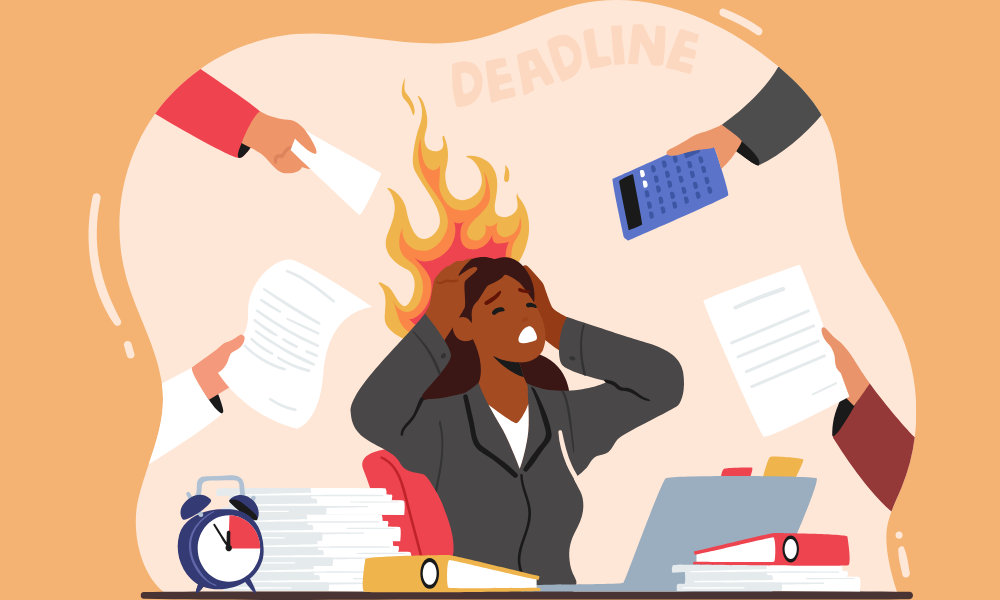
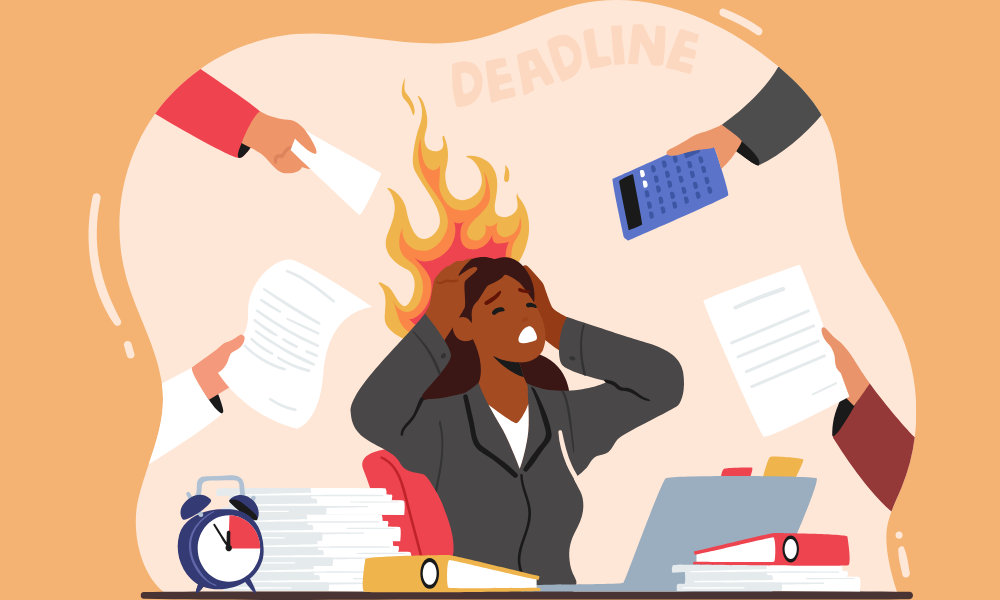
私の事業所の保険者が運営指導にあたり、ホームページで示している事前提出書類と当日の提出・提示書類です。
運営指導対策として、時間があるときに自事業所の保険者のホームページを確認しておくとよいですね。
- 運営規定
- 重要事項説明書
- 契約書
- 個人情報使用同意書
- 勤務形態と勤務体制一覧
- サービスに関する調書
- サービス計画の作成状況
- BCP作成状況(災害・感染症、それぞれに研修・訓練)
- 感染症対策の取り組み(指針・委員会・研修・訓練)
- 運営規定・重要事項説明書の掲示方法 ※ウェブサイトへの掲載(R7年度~義務化)
- 虐待防止の取り組み状況(指針・委員会・研修・新規採用時研修・担当者の設置)
- 個人情報の管理(USBメモリーやSDカードの使用状況)
運営規定・重要事項のウェブサイトへの掲載は令和7年度から義務化されています。
今年度から改正になっているものは、注意すべきポイントです。
実際に指導者がしっかり確認されていました。
- 勤務関係書類(出勤簿)
- 介護支援専門員証(写し)
- 緊急時、事故発生時、苦情対応等のマニュアルと対応状況
- BCP(災害・感染症)と指針(感染症・虐待)
- 委員会(感染症・虐待)の実施状況資料
- 研修・訓練(感染症)の実施状況
- 介護給付費請求書・介護給付費明細書
- 特定事業所集中減算に関わる減算適用判定に関する書類
- 特定事業所加算に関わる基準の毎月の遵守状況に関する書類
- 個人情報の管理状況(管理規定やマニュアル)
- ハラスメント対策実施状況
- 自主点検表
- サービスの提供を確認するための書類(ケースファイル)
私の事業所は「もうそろそろ運営指導来るよね…」と予想していたので、1~12までは概ねそろっていました。
一番大変なのは、サービスの提供を確認するための書類(ケースファイル)です。
きちんと支援していても「記録」がないと、「やっていない」とみなされてしまうこともあります…
この確認作業は所属するケアマネの人数が増えれば増えるほど大変になります。
私はこの難題に取り組むべき、運営指導までの準備計画を立てることにしました。
運営指導までの準備計画


居宅会議で自主点検表と集団指導の大切な箇所を共有する
運営指導の内容=自主点検表+集団指導
自主点検表と集団指導を網羅すること。
下記の記事【目次3】、”【運営指導対策】支援経過に記録すること” をケアマネ皆で共有しました。
優先度の高いケースをピックアップする
基本的に運営指導月の前月・前々月の記録をチェックすると通達されていました。
前月・前々月に下記に該当するケースを優先度の高いものとしてピックアップします。
- 加算算定(初回・入院時情報連携・退院退所・通院時情報連携・ターミナルケアマネジメント)
- 前月、前々月に上記加算算定がない場合は、遡って直近で算定しているケースファイル
- 軽度者レンタル
- 訪問リハビリと通所リハビリの併用
- 通所で口腔機能向上加算を算定
- 医療系サービス
限られた時間の中、通常業務をこなしながらのチェック作業は大変です。
すべてチェックできるかどうかわからないので、優先順位をつけることが大切です。
当日、どんな指導者が来るのかわからない。
「厳しい人だったらどうしよう…」
大袈裟ですが運を天に任せて、優先度の高いケースをチェックしていくしかありません。
しかし、この優先度の高いケースを確実にチェックしておいたことが、結果的にとても良かったのです。
そういえば、以前私が所属していた事業所で記録が追い付かないケアマネさんが、寝袋持参で泊まり込み作業をしていたのを思いだしました。
キャンプ感覚で楽しそうでしたが、さすがにそこまではしたくないです…
【準備計画】最初の10日間はケースファイルの自己チェック
最初の10日間は、優先度の高いケースを自己チェックする期間にあてました。
この4月に法人内異動で新しく着任したケアマネさんには、前任者の記録もチェックしてもらわなければならず、大変だったと思います。
自分の記録はチェックしやすいけど、他のケアマネの記録をチェックするのはしんどいですよね。
本当に皆頑張ってくれました。
【準備計画】10日目以降~運営指導当日まで、ケースファイルの他者チェック
私の事業所は、私を含めてケアマネが4人在籍しています。
先に述べた優先度が高いケースファイルの最終チェックは、私が行うことにしました。
運営指導に立ち会う人(管理者)が確認しておくのが良いのもありますが、最終的に何かあれば管理者である私の責任だと思ったからです。
「異動か…ボーナス減額?…どっちでもいいわ」って開き直るしかありません。
結果的には、やっぱり私が確認しておいてよかったと感じました。
指導者から「この記録はどこにありますか?」と質問されたとき、ある程度スムーズに答えることができたからです。
優先度が高くないケースは、他のケアマネ3人で相互チェックしてもらうようお願いしました。
相互チェックは別の主任ケアマネに指揮をとってもらうことで、私は優先度が高いケースに集中でき、当日の提出・提示書類の見直しや確認作業も行うことができました。
役割分担、大切ですね。
当日の打ち合わせ
運営指導は2時間の予定でした。
当日は、もちろん全員出勤。
運営指導が終わるまでは訪問を入れず、事務所待機。
運営指導に立ち会うのは私ですが、指導者がケースファイルを確認するとき、担当ケアマネでないとわからないことがあるかもしれないからです。
実際に担当ケアマネに来てもらい説明してもらう場面もありました。
そのほかにも足りない書類を持ってきてもらったり、皆で協力して乗り切ることができたのです。
運営指導はスムーズに進行し、予定通り2時間で終えることができました。
まとめ:運営指導の準備はチームで計画的に取り組もう!


居宅ケアマネ歴14年、今回が3回目の運営指導となった私。
これまでの経験をもとに、実際に行った準備計画の取り組みを紹介しました。
大切なことをまとめておきます。
- 事前の提出書類と当日の提出・提示書類を確認して準備する
- 運営指導までの準備計画を立てて実行する
- 居宅会議で自主点検表と集団指導の大切な箇所を共有する
- 優先度の高いケースをピックアップする
- 【準備計画】最初の10日間はケースファイルの自己チェック
- 【準備計画】10日目以降~運営指導当日まで、ケースファイルの他者チェック(役割分担)
- 当日の打ち合わせ(運営指導中はケアマネ全員事務所待機)
運営指導、本当に不安ですよね。
きちんと支援していても、記録が不十分で運営基準減算や報酬返還になってしまったら、ケアマネとしてのモチベーションが下がります。
そうならないように、事業所のケアマネ全員で役割分担し、チームで取り組む!
しっかりと対策して、問題なくクリアできるようにしておきましょう。
本記事に記載されているノウハウおよび手順は、筆者(主任介護支援専門員)の長年の実務経験と、特定の地域・事例における解釈に基づくものです。介護保険法、運営基準、地域の条例、および各保険者(市町村)の解釈は常に更新・変更される可能性があります。個別の判断や法的な解釈については、必ず所属法人の指導者、専門機関、または関係自治体にご確認のうえ、ご自身の責任においてご活用ください。
第2弾では、運営指導当日、指導者が確認された “特定事業所加算” の項目についてまとめています。運営指導対策に、是非、参考になさってください。