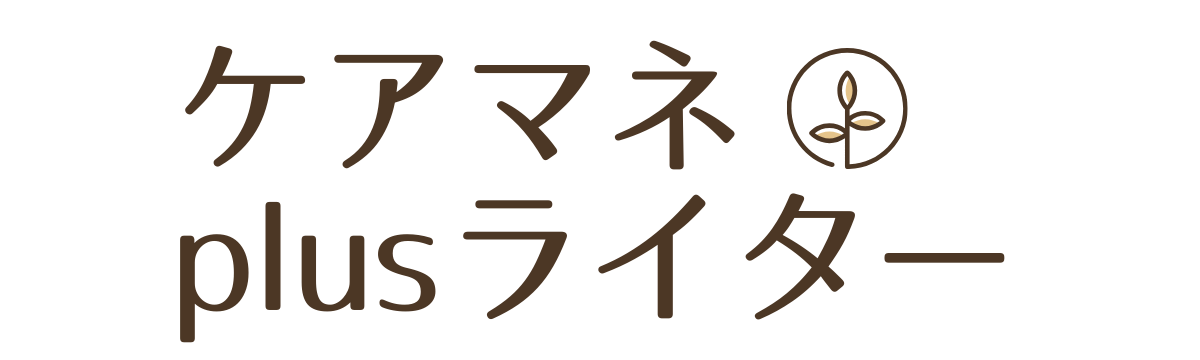運営指導は、ある日突然その連絡がきます。
「そろそろ運営指導くるかも…」と思っているケアマネジャーの皆さん、このような心配をしていませんか?
- 運営指導って何をどう準備したらいいの?
- 指導者から何を聞かれるの?
- 運営基準減算や報酬返還になったらどうしよう…
私もここ数年は同じような心配をしていました。
でもしっかりと準備と対策をしたことで、問題なくクリアできたのです。
居宅ケアマネ歴14年、今回が3回目の運営指導となった私。
この体験をもとに、日々頑張っているケアマネさんの参考になればと思い、運営指導の準備から実際に運営指導で確認された内容を発信しています。
第一弾は、運営指導【準備編】をお届けしました。
今回の第二弾は、運営指導【特定事業所加算編】です。
きちんと支援していても、記録がないだけでやっていないと見なされることもある運営指導。
しっかりと対策し、自信をもって運営指導に臨めるよう、是非、この記事を参考にしてください。
ただし、保険者によって注目するところに違いがあると思うので、そこはご理解の上、読んでください。
(ところどころ、私のつぶやき「BREAK」タイムが入ります。ご容赦ください…)
【運営指導】特定事業所加算について確認されたこと

私の事業所は、特定事業所加算Ⅱを取っています。
特定事業所加算Ⅱの算定要件である、以下のものを指導者が確認されました。
- 特定事業所集中減算書類
- 居宅会議録
- 毎月の遵守状況に関する記録
- 地域包括支援センターからの困難ケースの受け入れ
- 個人研修計画(研修報告書)
- ケアマネ実習生の受け入れ
- 他法人事例検討会
- ケアプランにインフォーマルサービスを位置づけているか
特定事業所集中減算
私の地域では、サービス事業所は程よく充足しています。
特別集中するような事業所もないので、書類さえあれば特に問題ありませんでした。
居宅会議録
週に1回居宅会議を開催し、下記について話し合われているか?
- ( a )現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
- (b)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
- (c)地域における事業者や活用できる社会資源の状況
- (d)保健医療及び福祉に関する諸制度
- ( e ) ケアマネジメントに関する技術
- (f)利用者からの苦情があった場合はその内容及び改善方針
- (g)その他必要な事項
私の事業所は居宅会議録に、該当するアルファベットを議題の横に入れています。
厳密に上記に該当しているかどうかまで、指導者は確認されませんでした。
少しかすっているぐらいでも上記アルファベットを議題の横に入れ、網羅していることにしています。
地域包括支援センターからの困難ケースの受け入れ
「地域包括支援センターから困難ケースを受け入れた場合、どのように管理しているか?」と指導者から質問されました。
困難ケースと言ってもどこからが困難なのか、線引きが難しいですよね。
「こちらで困難ケースだと思った利用者には、新規受け入れリストにチェックをつけ、遵守状況の書類に転記しています」と答えました。
指導者の質問の意図がイマイチよくわからなかったのですが、自信満々にそう答えると問題なかったです。
個人研修計画・研修報告書
研修関連では、下記のことを指導者が確認されました。
- ケアマネごと、年度末までに次年度の研修計画を立て、その振り返りや評価をしているか?
- 障害者、生活困窮者、難病患者、ヤングケアラー等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する研修に参加しているか?
私の事業所では、ケアマネごとの研修計画は年度末ギリギリですが作成し、評価は居宅会議の中で共有しています。
居宅会議録に評価したことを記録しておけば問題ありません。
昨年度から、障害者・生活困窮者・難病患者・ヤングケアラー等の研修に事業所のケアマネで手分けをして参加するようにしていました。
研修参加後は居宅会議で内容を報告し共有。
指導者が該当する研修報告書を確認されていました。
BREAKタイム
障害者・生活困窮者・難病患者・ヤングケアラー等の研修参加が特定事業所加算の算定要件に加わってから、特に「ヤングケアラー」の研修があると参加するケアマネさんが増えましたね。
ケアマネが知識を深めることは、とても大切だと思います。
ただ、この要件が加わったときに私は「またなんでもかんでもケアマネに押し付け」と思ってしまいました。
本来であれば、それぞれに専門家がいて連携し合える環境があることが、利用者にとっても、ケアマネにとっても一番よいと思うのです…
ケアマネ実習生の受け入れ
特定事業所加算を算定している居宅は、介護支援専門員実務研修の受け入れ協力事業所として登録されていると思います。
実際に指導したことがわかる書類よりも、年度初めに登録の申請をきちんとしているか?ということを指導者が確認されていました。
主任ケアマネの退職や異動などで変更になった場合、きちんと反映しておく必要がありますね。
BREAKタイム
私の地域では昨年度より、ケアマネ実習生を受け入れても「無報酬」に変更となりました。
この報酬は私の懐に入るわけではありませんが、事業所としての利益になることで、少なからず「やる気」に繋がっていたと思います。
上からは「残業削減」と言われます。
「無報酬」ということであれば、実習生受け入れのために時間をとられても、残業を増やすわけにはいきません。
でも、特定事業所加算の要件になっているのであれば、受け入れに協力せざるを得ないのです。
自治体の財政難で報酬がなくなったのだと思いますが、そのしわ寄せはいつも現場が負うことになります。
「ケアマネはタダで働かせても問題ないだろう…」という考えはそろそろ止めにしませんか?
それでなくても、ケアマネは処遇改善加算においては、いつも蚊帳の外なのだから…
他法人事例検討会の記録
他法人事例検討会はやってるだけではダメ。
きちんと年度末までに次年度の計画を立てて実行しなければならない...ということです。
計画を立てた記録(日程、開催場所、役割分担など)を残しておくようにしましょう。
ZOOMなどを使って、オンラインミーティングで計画をたてるのが効率的ですね。
研修もそうですが、事例検討会でも、障害者、生活困窮者、難病患者、ヤングケアラー等、高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討が必要です。
他法人事例検討会で上記に該当する事例をとりあげれば一石二鳥。
毎年、この手法で他法人事例検討会を行っています。
ケアプランにインフォーマルサービスを位置づけているか?
これは令和3年度の報酬改定から新たに加わったものです。
よくあるのが「配食サービス」「訪問マッサージ」「行政主体の個別ごみ収集」「民生委員の訪問」などではないでしょうか。
自主点検表には「多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護保険等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう)が包括的に提供されるよう居宅サービスの計画を作成していること」と書いてあります。
そして、「これらの必要性を検討した結果、居宅サービス計画に位置付けなかった場合、当該理由を説明できるようにしておくこと」となっているのです。
実際に運営指導でもインフォーマルサービスがひとつも入っていない居宅サービス計画について、「インフォーマルサービスの必要性について検討した記録は?」と指導者から質問がありました。
「サービス担当者会議の中で、他に必要な介護保険サービスやインフォーマルサービスがないか参加者で確認し、なかった場合は『残された課題』に『なし』と記載しています」と答えました。
私の答えで問題なかったのですが、指導者曰く、サービス担当者会議の要点に「検討の結果、現状の居宅サービス計画で充足しているため、インフォーマルサービスの必要性なし」と書いておくのがよいそうです。
BREAKタイム
近隣の居宅さんが運営指導を受けたとき、「当該地域の住民による自発的な活動によるサービス」の必要性を担当者会議で検討したのかどうか、しつこく聞かれたそうです。
「当該地域の住民による自発的な活動によるサービス」って、どこにある??
地域によってはあるのかもしれませんが、皆、自分の生活でいっぱいいっぱいで、特に要介護者に対して自発的に活動してくれるような住民って、そんなにいるのでしょうか?
確かに主任ケアマネには、地域課題の抽出と解決が求められています。
通院時、付き添ってくれる家族がおらず困っている利用者は多いものです。
地域ケア会議などでも一人暮らしの高齢者が増え、そういった課題が取り上げられたこともありました。
そこで「当該地域住民による自発的な活動によるサービス」を立ち上げて…なんて、今の居宅ケアマネには、そんなパワーと時間はありません。
令和6年度の報酬改定により、担当件数の上限が引き上げられ、参加しなければならない研修や委員会の増加、BCPなどの書類作成…
言うのは簡単、実行するのは至難の業です…
まとめ

居宅ケアマネ歴14年、今回が3回目の運営指導となった私。
その経験をもとに、運営指導【特定事業所加算編】を紹介しました。
大切なことをまとめておきます。
- 特定事業所集中減算書類
→きちんと書類があればOK - 居宅会議録
→議題に( a )~(g)までの要件を入れておく - 毎月の遵守状況に関する記録
- 地域包括支援センターからの困難ケースの受け入れ
→困難ケースか同課の判断は居宅で行い、月ごとに管理、転記 - 個人研修計画(研修報告書)
→年度末までに次年度の計画
→年度末に評価
→障害者・生活困窮者・難病患者・ヤングケアラー等の研修報告書 - ケアマネの実習生受け入れ
→介護支援専門員実務研修の受け入れ協力事業所として年度初めに登録 - 他法人事例検討会
→年度末までに次年度の計画を立てて実行
- 地域包括支援センターからの困難ケースの受け入れ
- ケアプランにインフォーマルサービスを位置づけているか
→位置づけしない場合、サービス担当者会議の要点にその理由を記載
冒頭にもお伝えしたように、保険者によって注目する部分に違いがあると思います。
「運営指導=自主点検表+集団指導」です。
私の体験はあくまでも参考であって、皆さんの保険者の自主点検表・集団指導をしっかり確認して運営指導に挑んでくださいね。
本記事に記載されているノウハウおよび手順は、筆者(主任介護支援専門員)の長年の実務経験と、特定の地域・事例における解釈に基づくものです。介護保険法、運営基準、地域の条例、および各保険者(市町村)の解釈は常に更新・変更される可能性があります。個別の判断や法的な解釈については、必ず所属法人の指導者、専門機関、または関係自治体にご確認のうえ、ご自身の責任においてご活用ください。
「そろそろ運営指導くるかも…」と不安なケアマネさんは、各種加算についてもまとめています。よかったら参考になさってください。