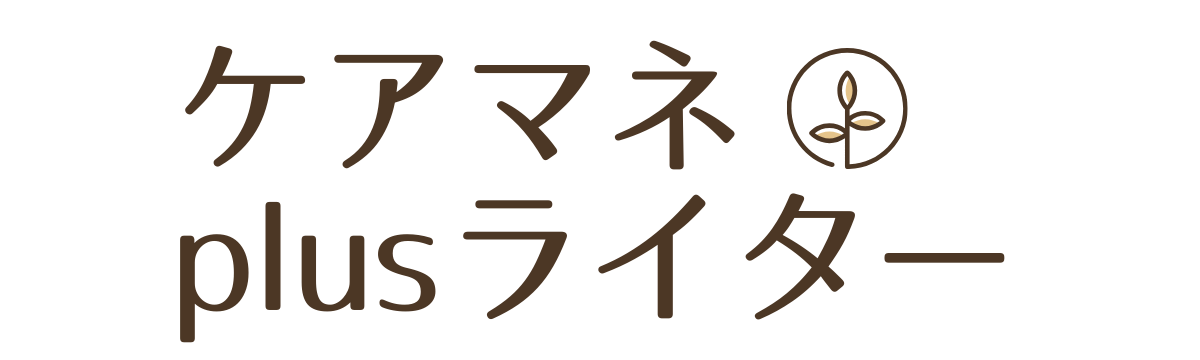ケアマネ試験に合格して、いざケアマネジャーになってはみたものの、このようなことで悩んでいませんか?
- 覚えることが多すぎて頭に入らない
- 利用者や家族にうまく説明できない、質問に答えられない
- ケアプランや医師宛ての照会など、文章が苦手
- やることが多すぎて何から手をつけていいかわからない
私は、A居宅で7年、そして今働いているB居宅で7年の経験があるケアマネジャーです。
これまで、多くのケアマネさん達と一緒に仕事をしてきました。
結論を言うと、今バリバリ仕事をしているケアマネジャーの誰しもが「はじめはみんなそうだった」ということ。
もちろん私も…
そして、この「何もわからない」状態を抜け出す一つの方法として、私がお勧めするのは「最初は人の真似をする」ことです。
なぜ私がそう思うのか、私の新人時代の失敗談も含めて、お話したいと思います。
悩んでいる新人ケアマネさんへ、少しでも考え方のヒントになれば嬉しいです。
一度にたくさん覚えなくてもいい
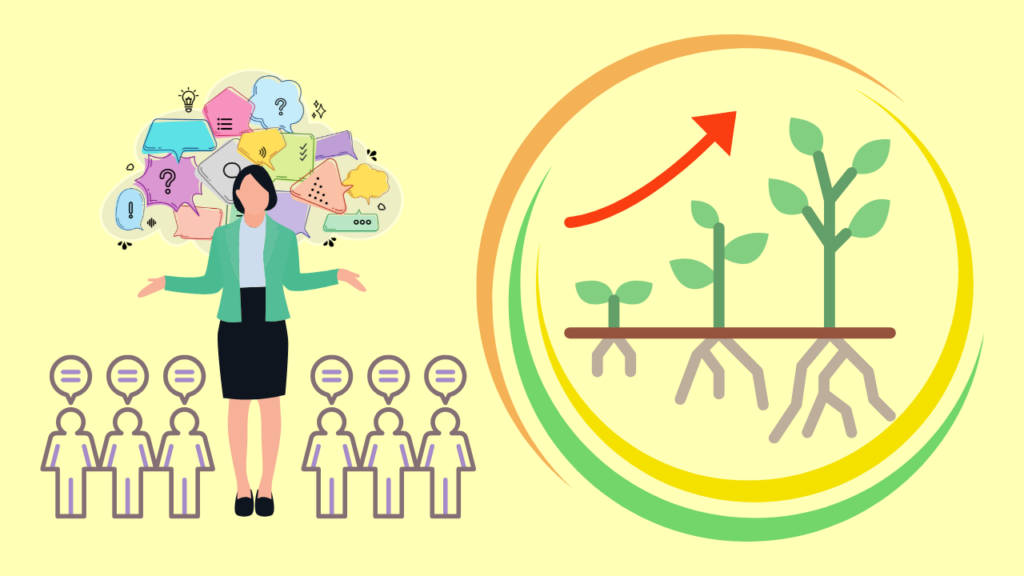
私の前職は、特別養護老人ホームの介護スタッフです。
転職して、居宅ケアマネ初日の午前中は管理者からケアマネ業務についての説明を受けました。
メモを取りながら話を聞きましたが、はっきり言ってほとんど何を言っているのかわかりませんでした。
管理者の説明が悪かったのではなく、私の頭が追いつかなかったのです。
前職が施設勤務だった私には、在宅介護のことはチンプンカンプン。
帰宅して、「提供票とは?」「利用票とは?」と、インターネットで検索したことを今でも覚えています。
ありがたかったことは、先輩ケアマネが「わからなかったら、また聞いて」といつも言ってくれたことでした。
なので、教えてもらったことでも、繰り返し聞いていたと思います。
でもさすがに3回以上聞くのは気がひけて、そういう時はその先輩が不在のときに、別の先輩ケアマネに聞いたりしていました。
忙しい先輩ケアマネには迷惑だったかもしれませんが、そうやって覚えていくものだと思います。
私は今、管理者で新人ケアマネさんを教える立場になっていますが、同じように「わからなかったら、また聞いて」と言うよう心掛けています。
まったく迷惑ではありません。自分もそうだったのですから…
【利用者や家族とのコミュニケーション】取り方のコツ
新人時代チンプンカンプンだった私が、どうこれを切り抜けていったのか、普段心掛けていることなども含めて、お話します。
先輩ケアマネの電話応対の仕方を観察して真似る
居宅ケアマネになった初日、先輩ケアマネが利用者や家族、サービス事業所相手に電話応対している姿を見て、「すごいなぁ」と感動したのを覚えています。
言葉使いや言い回し、強弱のつけ方、ときには謝罪の伝え方なんかも、聞いていて自分が感じ良く聞こえたものは真似してみようと思いました。
ケアマネ業務でなくてもそうですが、最初は「良いものを真似る」というのが一番手っ取り早く身につく方法だと思うのです。
ある程度身についてから、自分のアレンジを加えていく。
料理と似ていますね。最初はレシピを見て…そのうち、違う材料や調味料を加えてみる…みたいな。
自分が喋ることより、利用者や家族の話を聞くことに注力する
ついつい、あれもこれも説明しなければ…と自分ばかり喋ってしまうこと、あると思います。
これは私の新人時代の失敗談です。
一人で新規利用者の訪問をするようになった頃の話です。
とある利用者さん宅に伺い、キーパーソンであるご家族に私が初めにした話は契約書と重要事項説明書の内容でした。
そのご家族より、「まずはこちらの話を聞いてほしい」とお叱りを受けたのです。
私は、「まずは契約..」と焦る気持ちがありました。
初めて親が介護を受けることになったそのご家族にとっては、今、困っていることや不安なことを、まずは聞いてほしかったのだと思います。
利用者やご家族は、自分の話を聞いてくれる人の方が安心できるのだと学びました。
この反省は今でも忘れていません。
なので、新人のうちはうまく喋れなくても、利用者やご家族の話を聞くことに注力できれば大丈夫。
無理にうまく喋ろうとしなくても、月日が経てば徐々に慣れていきます。
言葉につまるときは利用者や家族の言葉を復唱しながら時間を稼ぐ
新人のうちは利用者や家族に、あれもこれもと説明するのは大変ですよね。
「ゆっくり喋る」を心掛けるとよいと思います。
ゆっくり喋るほうが次に何を言おうか、考えながら喋ることができます。
私は今でも、答えに困るときは、利用者や家族の言葉を復唱したり、「○○なことがあったんですねー」と語尾を伸ばしたりして、時間稼ぎをしつつ、会話をしています。
復唱することで自分の頭も整理でき、案外、そのほうが良い答えが浮かんできます。
【利用者や家族からの質問】答えがわからないときは、持ち帰って後で返事をする
利用者や家族からの質問で、はなからわからないことは、「事務所に持ち帰って、きちんと調べてからお返事しますね」で大丈夫です。
「きちんと調べて」と言われるると、なんだか信用できませんか?
「きちんと調べて」があるかないかで印象が変わると思います。
逆の立場でも「自分のためにきちんと調べてくれるんだ」と、なんだかうれしいですよね。
ほんの些細な一言ですが、是非、活用してみてください。
ケアプランや医師宛ての照会などの文言は良いと思ったものを真似る
ケアマネの実務研修でケアプランについてはある程度学んだとしても、医師宛ての照会などは、かしこまった文章で難しいですよね。
私は先輩宛ての照会の返信がきたとき、先輩に渡す前によくこっそり見ていました。
こう書けばわかりやすいなって思ったものは、そく真似る。
テンプレ化する感じです。
ケアプランの文言に関しても、インターネットで検索すれば、たくさんの文例が出てきます。
本当に良い文例が多いですよね。
「私が言いたかったのはこれだ!」という文言がきっと見つかると思います。
新人のうちは、いろんなものを見て学ぶ。
私が最初に働いたA居宅はたくさん先輩がいたので、いろんなケアプランを見て参考にしていました。
訪問が近い利用者に関する【照会・サービス調整・ケアプラン原案・利用票】を優先
ケアマネの実務研修では「アセスメント」→「課題整理総括表」→「ケアプラン原案作成」の順に学ぶのではないかと思います。
私がケアマネになった頃は、この「課題整理総括表」なるものはありませんでした。
この順番でケアプラン原案を作っているケアマネさんは、ほぼいないんじゃないかと思います。
担当利用者が増えてくると尚更ですし、急な対応が必要な利用者が出てくると、とてもじゃないけど手がまわりません。
私は「アセスメントは頭の中、担当者会議が終わってから、作成する」ことがほとんどです。
大きい声では言えませんが、課題整理総括表に関しては、これから受けていくケアマネ更新のための法定研修で活用できれば十分だと思います。
何から手をつけてよいのかわからないときは、訪問が近い利用者の【照会・サービス調整・ケアプラン原案・利用票】を最優先にします。
自分のスケジュールを見ながら、訪問が近い利用者からこなしていくイメージです。
これができれば、そのほかの書類や支援経過は、時間があるときにやるのでよいと思います。
まとめ:新人のうちはいろんなものを見て、良いと思うものを真似よう

今回は、いざ居宅ケアマネになってはみたものの、何もわからないと悩んでいる新人ケアマネさんに向けて、少しでもなにかのヒントになればと、私の新人時代の失敗談を含めてお話をしました。
前職が施設勤務で在宅介護がチンプンカンプンだった私でも、14年間居宅ケアマネをやってこれました。
最初は、いろんなものを見て、よいと感じたものを真似、少しずつ自分の成長に繋げていってくださいね。
もしも、「ケアマネの仕事、自分には向いていない?」としんどくなったら、こちらの記事を読んでください。これまでたくさんのケアマネさんを見てきた経験をもとに、書いています。