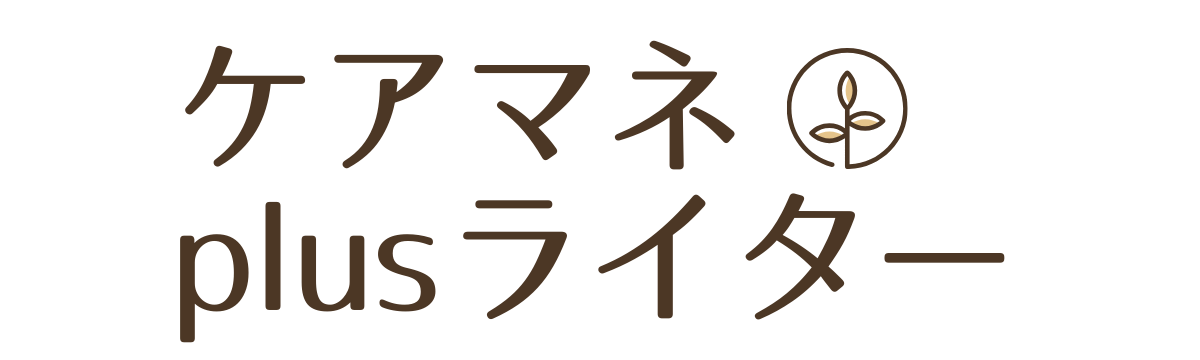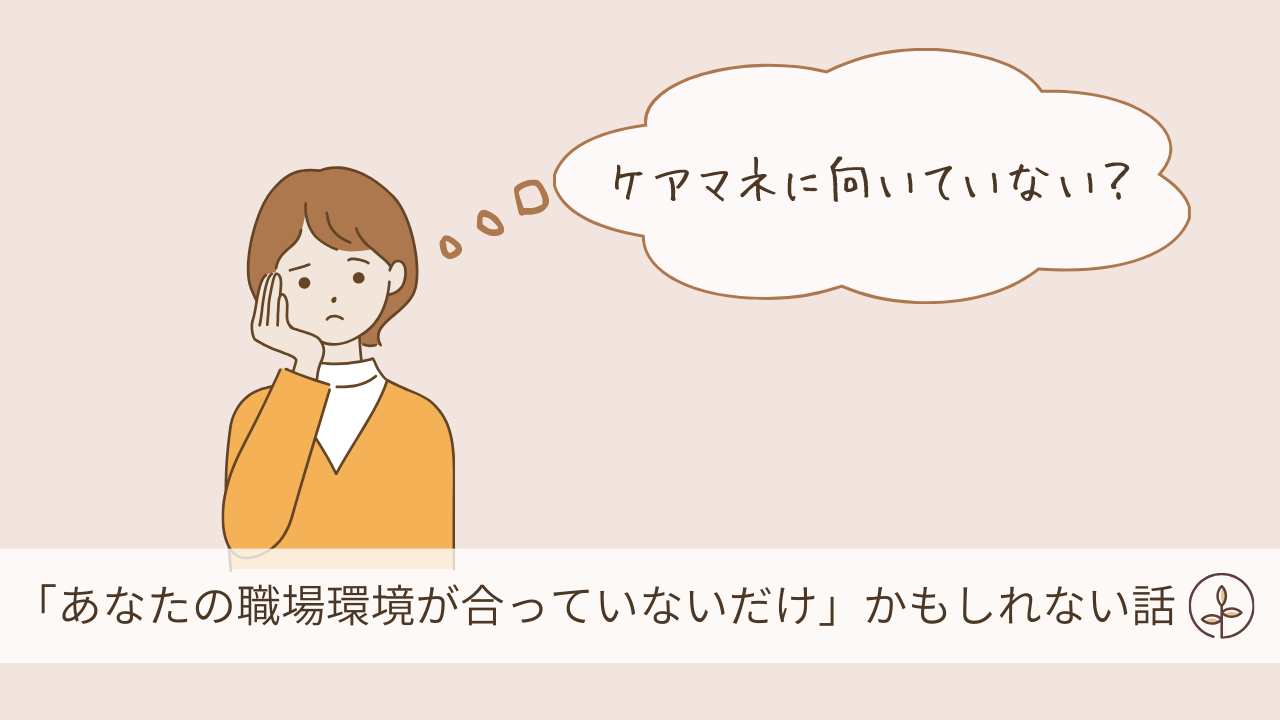地域の会議から戻ってきた後輩が、私に言いました。
 後輩ケアマネ
後輩ケアマネ○○事業所のケアマネAさん、今月末で辞めるんですって。
ケアマネ向いてないから、ヘルパーに戻るって言ってましたよ。
私もAさんとは、何度か研修や会議でお話したことがあります。
Aさんは、2年目になったばかりの謙虚で感じのよいケアマネさん。



なんで辞めてしまうんだろう…もったいない…
私は、居宅介護支援事業で管理者をしている主任ケアマネジャーです。
これまで多くのケアマネさんと一緒に仕事をし、他事業所のケアマネさん達とも交流しています。
実は、「ケアマネに向いていない」と悩む原因が、「職場環境があなたに合っていないだけ」ということも少なくありません。
今回は、私の経験を踏まえ、「今の職場環境が合っていない」具体的な実例を交えながら、まとめます。
「ケアマネに向いていない」と悩みを抱えるケアマネさんに、少しでもヒントになればうれしいです。
ちょっと意地悪に感じる先輩ケアマネがいる環境


私も新人時代、ちょっと意地悪に感じる先輩ケアマネに出会いました。
在籍している10人のケアマネのうち、1人がそうでした。
その先輩が私のパソコンをのぞき込み、「何それ?研修で教わってきたんじゃないの?」と、よく嫌味を言われたものです。
これまでに数人のケアマネが耐え切れずに辞めていったと、後になって知りました。
そんな先輩に出会っても、「自分が悪い」と抱え込みすぎなくて大丈夫です。
もし今辛くても、先輩が変わるか、あなたが環境を選び直すことで状況はきっと変わっていくからです。



私の場合、時間の経過とともに、他の先輩ケアマネが力になってくれたことで環境が少しずつ変わりました。
上司が主観的すぎる評価をする環境
実際に私が一緒に働いているケアマネにも、前の部署で“主観的すぎる評価”によってキャリアを歪められてしまった人がいます。
異動前の上司からは、「レベルが低い」「いつまでたっても自分で判断できない」といった評価を受けていました。
ところが、私の部署に異動してきて、直属の部下として一緒に仕事をしてみると、印象はまったく違いました。
そのケアマネは、真面目で責任感が強く、自分で学ぼうとする意欲も持っています。
むしろ、丁寧に仕事に向き合うタイプの人でした。
後になってわかったのは、前の上司が十分な指導やフォローをしていなかったこと、そしてその上司自身も業務が回せていない状態だったという事実です。
適切でない評価が、1人のケアマネの成長の機会を奪い、キャリアを潰しかけてしまうこともあります。
本人の能力に問題があるのではなく、その上司の主観によってレッテルを貼られてしまう、そうした理不尽さに胸が苦しくなります。



私自身も今は上司という立場で、主観的な評価に流されないよう気をつけようと強く思うようになりました。
1人の評価が必ずしも正しいとは限らない。
もし今のあなたが苦しんでいるなら、それは「あなたの力不足」ではなく、「評価する側の視点」が歪んでいるだけなのかもしれません。
まとめ:それはあなたのせいではなく、環境の問題かもしれない


人間関係や評価のされ方は、職場によって本当に違います。
先輩との相性が悪かったり、上司の主観だけで能力を決めつけられてしまったりすると、「自分は向いていないのかも…」と感じてしまうのも無理はありません。
でも、それはあなたの実力が足りないからではなく、「環境の方があなたに合っていないだけ」ということも実際にああるのです。
意地悪に感じる先輩がいる場所を離れたら、急に働きやすくなる人がいます。
評価する上司が変わっただけで、本来の力を発揮できるようになる人もいます。
今の悩みを「自分が向いていない」と決めつけず、環境との相性という視点も、ぜひ忘れないでください。
あなたの良さや強みをちゃんと見てくれる人達がいる環境こそ、ケアマネとしての力は自然に伸びていくと思います。
最後まで、この記事を読んでくれたあなたにご報告しておきます。
この記事に書いた「上司の主観的すぎる評価」によって、キャリアを歪められていたケアマネさん。
私の部署に異動してきて8カ月が経ちました。
最初は自信なさげに電話対応していたけど、今ではしっかりと対応して、表情も明るくなりました。
人伝てに「居宅に異動してよかった」とそのケアマネさんが言っていたと聞きました。
「いずれは、主任ケアマネを任せたい」そう思えるケアマネさんです。
人は環境でこんなに変わるということを、私自身が実感した出来事でした。
もし、ケアマネの仕事がそれでも辛いという方は、新しい視点や選択肢を知ることで、少し気持ちが楽になるかもしれません。こちらの記事も参考にしてください。