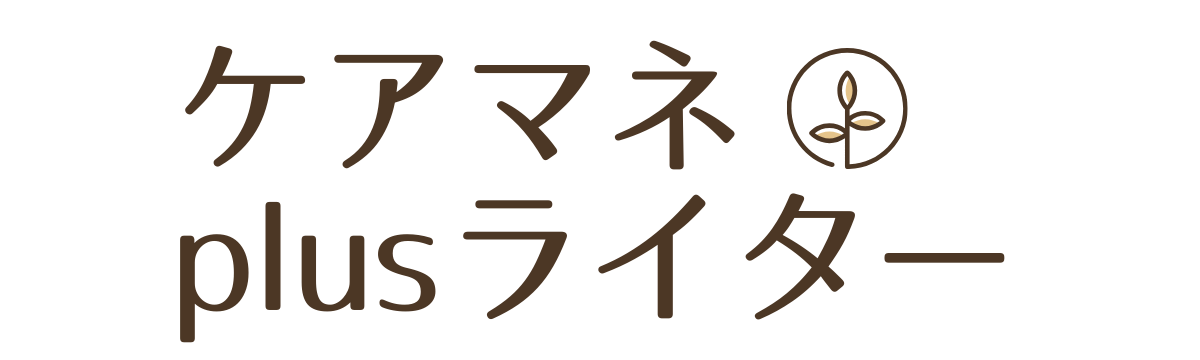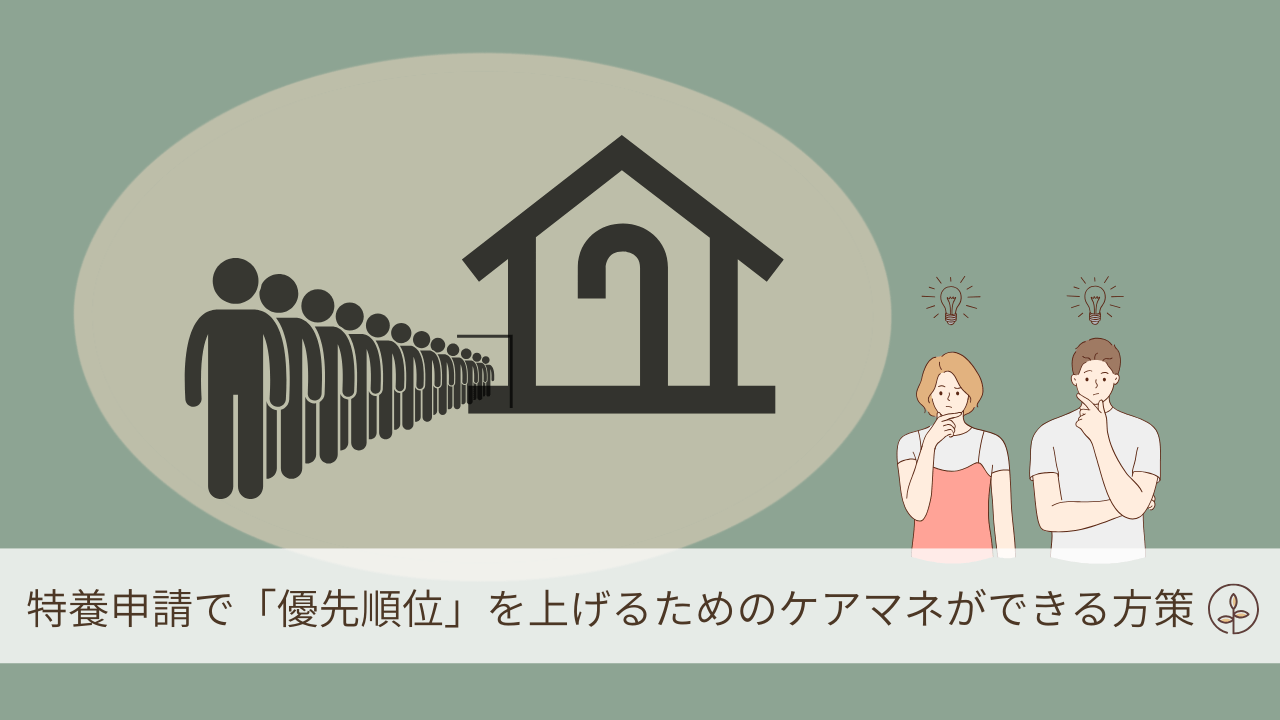- できるだけ早く特養に入るにはどうすればいいの?
- 費用を抑えたいから特養以外は考えられない
在宅生活の継続が難しくなってきたとき、利用者や家族からこのような相談で頭を悩ませているケアマネさん、意外と多いのではないでしょうか。
特別養護老人ホーム(以下、特養)は、介護度が高く在宅生活が難しくなった高齢者にとって、安心して長く暮らせる場所のひとつです。
比較的費用が安いことから人気が高く、入所待ちが多いため、すぐに入れるとは限りません。
筆者は従来型特養に2年間、ユニット型特養に2年間の勤務経験があり、ケアマネさんから寄せられる申請書をもとに面談~入所判定会議まで関わっていました。
現在は居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーとして、逆の立場から利用者の特養申請をサポートしています。
施設側・居宅側、両方の視点を持っているからこそ、見えてきたポイントがあります。
この記事では、特養申請で優先順位を上げるためのケアマネができる方策をご紹介します。
これまでの私の経験から、特養から声がかかりやすくなる秘策も「ここだけの話」としてご紹介します。
- 入りやすい特養の情報収集
- 【複数・新設・家族宅から近く】の特養に申し込む
- 【秘策!】特養申込書の特記事項に「必要性+α」を記載する
- 待機期間に併設のデイサービスやショートステイを利用する
まずは、特養申込から入所に至るまでの流れを知っておこう
まずは、申込から入所に至るまでの流れを理解しておきましょう。
ヘルパー出身のケアマネさんなどは、知らない方が多いと思うので、一般的な流れをステップごとに解説しておきます。
入所したい施設を決定し、入所申込書、その他必要な書類(自治体や施設ごとに指定されている)を提出します。
担当のケアマネジャーが施設に提出することが多いですね。
申込した施設では、緊急度や必要性を評価し、結果に応じて入所待機順を決定します。
評価方法は、施設により異なります。
(例)
- A・B・Cの三段階評価(Aが一番優先度が高い)
- 点数評価(100点が一番優先度が高い)
 筆者
筆者私が最初に勤務した特養は1の方式、次に勤務した特養は2の方式でした。
待機期間を経て入所優先度の高い方より、順に施設から担当のケアマネジャー、もしくは家族に連絡が入ります。
この段階では、まだ入所が決定したわけではありません。



面談後に入所判定会議で不可になる可能性もあるので、まだ油断できません。
利用者・家族に対し、施設の職員(生活相談員や看護師など)が面談を行います。
通常、利用者宅で行いますが、入院中や他の施設にいる場合は、そこへ施設の職員が訪問することもあります。
この面談で、利用者の現在の心身状態、生活状況、医療的なニーズなどを最終確認します。
事前に、健康診断書や診療情報提供書などの医療情報の提出を求められる場合があります。
利用者側も施設の体制や生活に関する疑問などは、施設の職員に確認しておくのがよいでしょう。
施設では聞き取った情報をもとに、入所の可否を検討します。
施設の受け入れ態勢と入所者の状況が合致すると判断された場合、正式な入所が決定です。
その後、入所日の調整、持ち物の準備などを行います。



ここまで来ると安心ですね。
施設との契約書や重要事項説明書などの書類を取り交わし、入所となります。
入りやすい特養の情報収集
もし、「何年も待てない」「できるだけ早く特養に入りたい」と利用者から要望がある場合は、どの施設を申し込むかの段階で情報収集しておくことをお勧めします。
希望する施設に直接聞いてみるとよいですよ。
私の過去の経験ですが、要介護3の方の特養入所をサポートしていた際、事前の電話相談で施設側から得た情報です。
- 「うちは、ほぼほぼ要介護4か5でないと入所は難しいから、今、要介護3なら4になってから申し込んだ方がいいですよ。待機者は500名ほど。今、申し込むと、申込書が埋もれてしまうだけですよ」
- 「この前、要介護3の方が入所したばかり。次は要介護4か5の方が選ばれると思います」



繋がりのある特養の相談員さんであれば、裏側情報まで教えてくれたりします。
もし、担当の利用者が要介護3だったとしても、特養に入れるケースはたくさんありますので、諦める必要はありません。
【複数・新設・家族宅から近く】の特養に申し込む
ここでは、現役のケアマネジャーである私が実践している、特養に申し込むときの「よくある方策」から「意外にそうなの?」という方策をご紹介します。
【よくある方策】複数の特養に申し込む
1か所より、複数申し込む方が入所の確率はあがります。
私の経験では、3~4か所の特養に申し込む方が多いです。
ご本人が男性の場合、従来型特養(多床室)よりは、ユニット型特養(個室)に申し込む方が入れる可能性が高くなります。
男女の平均寿命の違いなどから、古くからある従来型特養の多床室は、女性部屋の割合が多いからです。
施設費用は、従来型特養(多床室)の方が安くすみます。
「できれば従来型特養(多床室)がいいいけど、無理ならユニット型特養でもOK」とう方には、両方に申し込むこともできます。
【よくある方策】新設の特養は狙い目
もし、「新設の特養が建つ」という情報があれば、これは狙い目といえるでしょう。
多くは、開設の半年前あたりから入所申込を受け付けています。
入所定員が多い施設であればあるほど、入所できる確率は高いです。
すでに特養の申込をしている場合も、「新設の特養が建つ」といった情報があれば、申込んでみるとよいでしょう。



現在はユニット型個室の普及が進んでいるため、新しく開設される特養のほとんどは、ユニット型特養になります。
【意外にそうなの?という方策】家族宅から近くの特養に申し込む
例えば、本人がA市のB区で1人暮らし、家族が同じA市のC区に居住。
B区からC区まで少し距離がある場合、家族が居住するC区にある施設を申し込むのも有効だと思います。
特養は原則として、「終の棲家」としての長期入所が可能な施設です。
必要な物品の差し入れや、季節に応じた衣類の入れ替えなど、施設からお願いされることもあると思います。
家族が施設に足を運びやすい方が、施設にとっても心強いです。
最近はどの施設も “地域とのつながり” を大切にしています。
ご家族がその地域に居住されていることは、少なからず強みのひとつであると思います。
ただし、本人宅と家族宅が都道府県を跨ぐなど、かなり遠方の場合、施設職員がご本人の面談に行くのが難しくなることも考えられます。事前に施設に確認するほうがよいですね。
【秘策!】特養申込書の特記事項に「介護の困難さや緊急性+α」を記載する
ここでは、方策ではなく、秘策「ここだけの話」をご紹介します。
特養の申込書は各自治体により、様式はそれぞれ異なりますが、「特記事項」という欄が設けられています。
特記事項には「優先入所を必要とする特別な理由」について、個別の事情を記載することができます。
「特養から入所に至るまでの流れ」STEP2で解説した、評価が同じ人の場合、施設側はこの特記事項を見て、面談の候補者を検討する可能性が高いと思われます。



「特記事項」で差がつく。実際に私が勤務していた2つの特養、どちらもそうでした。
通常、「介護の困難さや緊急性」だけを、特記事項に記載するケアマネさんがほとんどです。
私はこれまでの経験から、「介護の困難さや緊急性+施設入所することで本人・家族のQOLの向上」を特記事項に記載することを実践しています。
例えば、「介護の困難さや緊急性」だけの記載なら、このような感じになります。
認知症が進み、妻が少し目を離した隙に外に出て、大声で叫びながら近所の家のドアを叩くようになった。妻はトイレに行くことすら気が気ではなく、精神的な疲弊から体調を崩している。このままでは夫婦共倒れになる可能性が高く、優先入所を必要とする。
私が実践する「介護の困難さや緊急性+施設入所することで本人・家族のQOLの向上」を意識するとこんな感じに。
認知症が進み、妻の姿が見えなくなると不安になり、外に出て妻を探すようになった。大声で近所のドアを叩くので、妻はトイレにも行けず体調を崩し、夫婦共倒れになる可能性が高い。デイサービスでは、スタッフの見守りや声かけにより、比較的落ち着いて過ごしている。施設に入所し、常時の見守りや声かけがある中で過ごすことが本人の安心に繋がる。妻も体調を整え、面会を通じて本人と良好な関係を続けていくことができる。
例②では、「施設入所することで本人・家族のQOLの向上」を赤字で示しています。
夜間眠らずに探し物をずっとしている。日中は眠気が強く、食事がきちんと摂れない。自宅内は這って移動するが、トイレに間に合わず、汚れたままになっている。在宅サービスを限度額いっぱいまで利用しているが、1人暮らしを継続することが難しい。他区に住む子が1時間かけて、時々訪問しているが、就労があるため負担が大きく、優先入所を必要とする。
もともと商売を営んでいた本人は社交的で世話好き。施設に入所し、日中に多くの人と関わり、活動量を増やすことで生活リズムがつく。子の近くの施設に入所できれば、子は面会に行きやすく、安心して仕事も続けることができる。



私はこの書き方を意識するようになってから、施設から面談の声がかかることが一気に増えました。
施設側も「施設に入ってからの見通し」が示されている方が、よりその人のことがイメージしやすく、印象に残ります。
特記事項に「施設入所することで本人・家族のQOLの向上」をプラスすることで、「ご本人やご家族のために支援したい」と施設側に思ってもらえれば、面談の声がかかる確率もあがるのではないかと思っています。



特記事項は本当に大切ですよ。
待機期間に併設のデイサービスやショートステイを利用する
申込をした施設にデイサービスやショートステイが併設されている場合は、利用してみるのもよいでしょう。
利用者や家族にとって、施設の雰囲気や職員の対応などがわかり、入所後の生活がイメージしやすくなります。
施設側もご本人の状態や生活スタイルを把握しやすくなり、入所に繋がるケースは多いです。
ただし、ご本人の状態によっては、併設のデイサービスやショートステイを利用することで、かえって入所の声がかかりにくくなってしまうケースもあるので注意が必要です。
(例)職員へのハラスメント行為・他の利用者に危害を及ぼす
施設にもよるかもしれませんが、例示のような行為がある利用者の方の施設入所は結構厳しいです。先に主治医に相談するのがよいと思います。



以前勤務していた特養では、セクハラ行為のある利用者は入所判定で不可になっていました。
まとめ:特養でないと困る利用者へ、できる方策(秘策)を試してみて


特養での勤務経験を持ち、現在は居宅介護支援事業所でケアマネジャーとして特養の申請をサポートしている筆者が、特養申請で「優先順位」を上げるためのケアマネができる方策をご紹介しました。
私が実践している、特養から声がかかりやすくなる秘策も「ここだけの話」としてご紹介しましたが、この秘策はこの記事を見ているあなただけに留めて試してみてください。
なぜなら、この秘策を多くのケアマネさんがするようになると、「特記事項」に差がつかなくなるからです。
本当は記事にするのも悩んだのですが、今はまだひっそりと公開しています。
特養の入所は、申込から実際に入るまでに時間がかかるのが現実。
でも、ちょっとした情報収集や申込の工夫(方策と秘策)、待機期間中の実践などから、声がかかる可能性が高まるかもしれません。
「どうしても特養でないと困る」という利用者の方がいれば、この記事を参考にできる方策を試してみてくださいね。
本記事に記載されているノウハウおよび手順は、筆者(主任介護支援専門員)の長年の実務経験と、特定の地域・事例における解釈に基づくものです。介護保険法、運営基準、地域の条例、および各保険者(市町村)の解釈は常に更新・変更される可能性があります。個別の判断や法的な解釈については、必ず所属法人の指導者、専門機関、または関係自治体にご確認のうえ、ご自身の責任においてご活用ください。