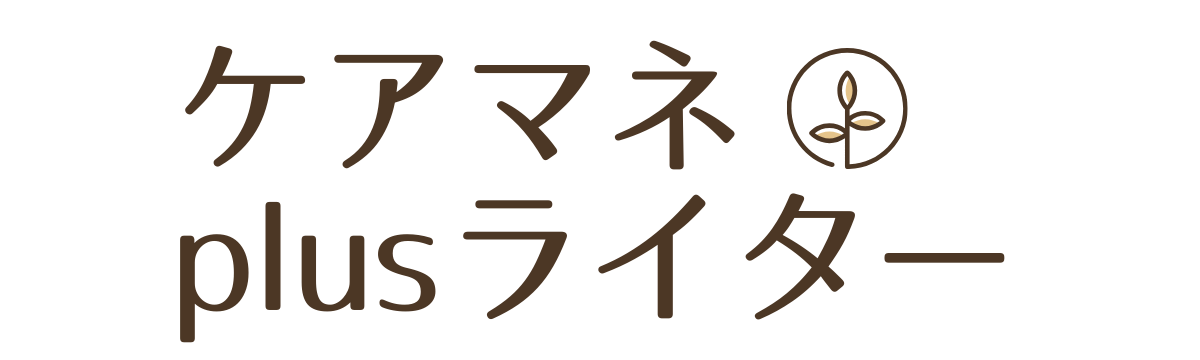高齢になっても、できるだけ住み慣れた自宅で暮らしたい…そう願う方はとても多いと思います。
しかし、生活する上で階段昇降が必須となる住居の場合、加齢とともに、いつまで住み続けられるのか…と不安になる高齢者の方は多いのではないでしょうか。
- エレベーターのない2階以上の集合住宅
- 玄関まで5段以上の階段がある戸建て住宅
- 水回りが2階にある戸建て住宅
階段は若い頃には何気なく昇り降りできても、加齢により、筋力・バランス能力が低下すると大きな負担となります。
今回は14年間、居宅介護支援でケアマネジャーをしている私の経験から、住居タイプごとの備えや、階段昇降ができなくなったときの対処法をご紹介します。
 筆者
筆者目次から、ご自身の住居タイプを選んで読むことができます。
【エレベーターのない2階以上の集合住宅】備えと対策


近年の集合住宅ではエレベーター付きが主流となっていますが、古いアパートや団地では、今でも階段のみという建物が少なくありません。
高齢になると、荷物を持って階段を昇ることが大きな負担となります。
外出や通院が億劫になり、閉じこもりがちになられる方も多いでしょう。
日々の活動が少なくなると、筋力や体力が低下して、悪循環に陥りやすくなります。
- 運動習慣をつけて、筋力や体感バランスを鍛える
- 介護保険サービスをご利用の方は、デイケアや機能訓練特化型デイサービス、訪問リハビリなどを利用する
- 手すりをしっかり握って階段の昇り降りをする
- 転倒や転落を予防することが大切
- 雨の日や夜間は特に注意する
- サンダルや滑りやすい靴は避ける
- まだ元気なうちに、1階やエレベーターが設置されているところに住み替える
- 公営住宅などは自治体に住み替えの相談をする
エレベーターのない2階以上の集合住宅に住む高齢者の方で、今の住居にできるだけ長く住み続けたいと思うなら、運動習慣をつけることがとても大切です。
日常の家事で手を使えば、握力が鍛えられ、手すりをしっかりと握ることができます。
私が担当する利用者さんは、エレベーターのない公営住宅の5階に住んでいたのですが、住み替え制度を利用して同じ団地内の1階に転居されました。



1階に転居したことで、散歩に出やすくなり、今でも足取り良く歩いておられます。
- 家族などに手伝ってもらい、1階やエレベーターが設置されているところに住み替える
- 在宅サービスをフル活用する
- 介護保険の訪問系サービス、訪問診療、配食サービス、個別配達など
- 施設入所を検討する
階段昇降ができなくなったタイミングで、子が引き取って同居したり、施設に入所された方もおられました。
しかし、中には子供との同居や施設入所も難しいといったケースも意外と多いものです。
在宅サービスをフル活用して、外出せずに過ごすという方法もできなくはないですが、ご本人にとって、あまり好ましくはありません。
ご家族などの協力で、1階やエレベーターが設置されているところに住み替えができれば、デイサービスに通うなど、生活の幅を広げることができるでしょう。
【玄関まで5段以上の階段がある戸建て住宅】備えと対策
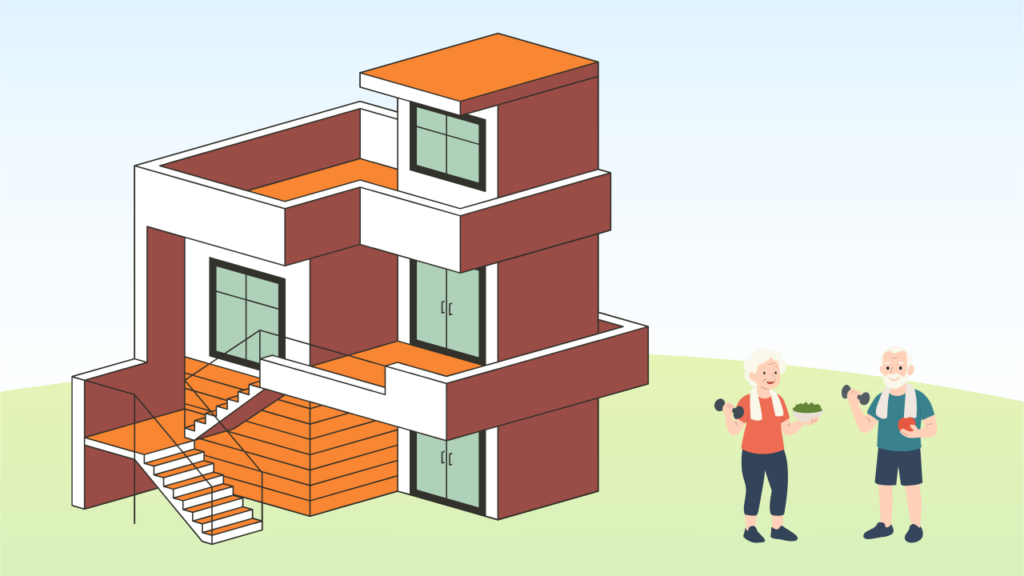
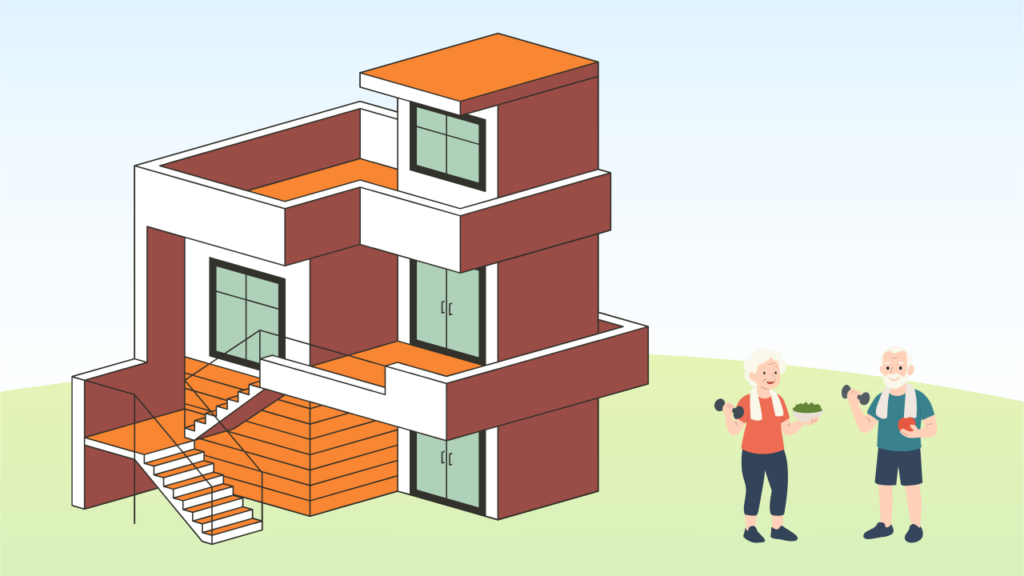
戸建て住宅では、門扉や道路から玄関までに階段があるケースが多く見られます。
階段が長くなればなるほど、筋力や体力が落ちた高齢者にとっては大きな障壁です。
- 住宅改修で手すりを設置する
- 介護認定を受けている方は、20万円以内の工事が1割~3割の自己負担で利用できる
- 階段の勾配や構造によっては、住宅改修が難しい場合がある
- 運動習慣をつけて、筋力や体感バランスを鍛える
- 介護保険サービスをご利用の方は、デイケアや機能訓練特化型デイサービス、訪問リハビリなどを利用する
- 雨の日や夜間は特に注意する
- サンダルや滑りやすい靴は避ける
- 転倒や転落を予防することが大切、戸建ての場合は発見が遅れる場合がある
- 賃貸の戸建ての場合は、元気なうちに住み替えを検討する
- バリアフリー、高齢者住宅への住み替え
階段が急だったり、踏み面が狭い場合には転倒や転落のリスクが高まります。
手すりがない場合は、早いうちから設置を考える方がよいでしょう。
賃貸の戸建ての場合は、住み替えを検討することができるかもしれませんが、持ち家の場合には、そう簡単にはいきません。
運動習慣をつける、サンダルや滑りやすい靴は避けるなど、転倒予防に重点をおくことが大切です。
- 屋外用の階段昇降機や段差解消機などを設置する
- 階段の勾配や構造によっては、設置が難しい場合がある
- 玄関以外に出入り可能な方法がないか検討する
- 掃き出し窓から出入り可能な場合もある
- 在宅サービスをフル活用する
- 介護保険の訪問系サービス、訪問診療、配食サービス、個別配達など
- 施設入所を検討する
屋外用の階段昇降機や段差解消機については、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
ケアマネジャーを通じて、福祉用具の専門家が、実際に階段の構造を見て判断してくれます。
どのような種類があるか、費用がいくらかかるかについては、👉「ヤマシタ すぐきた」を参考にされるとよいです。



ヤマシタは、私もケアマネ業務でお世話になっている、信頼できる福祉用具事業所の一つです。
階段が3段程度であれば、屋外用スロープを置いて車椅子で移動する方法もあります。階段が5段以上の場合は、スロープがかなり長くなるので取り扱いが難しく、現実的ではありません。
視点を変えてみると、もしかしたら、玄関以外にも出入りできる場所があるかもしれません。



私が以前担当していたお宅では、掃き出し窓から住宅改修でスロープを取り付け、外出できるようになったケースがありました。
在宅サービスをフル活用して閉じこもりとなる生活は、できるだけ避けたいものです。
ケアマネジャーや福祉用具の専門家に相談しながら、出入りできる方法について知恵を絞りだしてみましょう。
【水回りが2階にある戸建て住宅】備えと対策
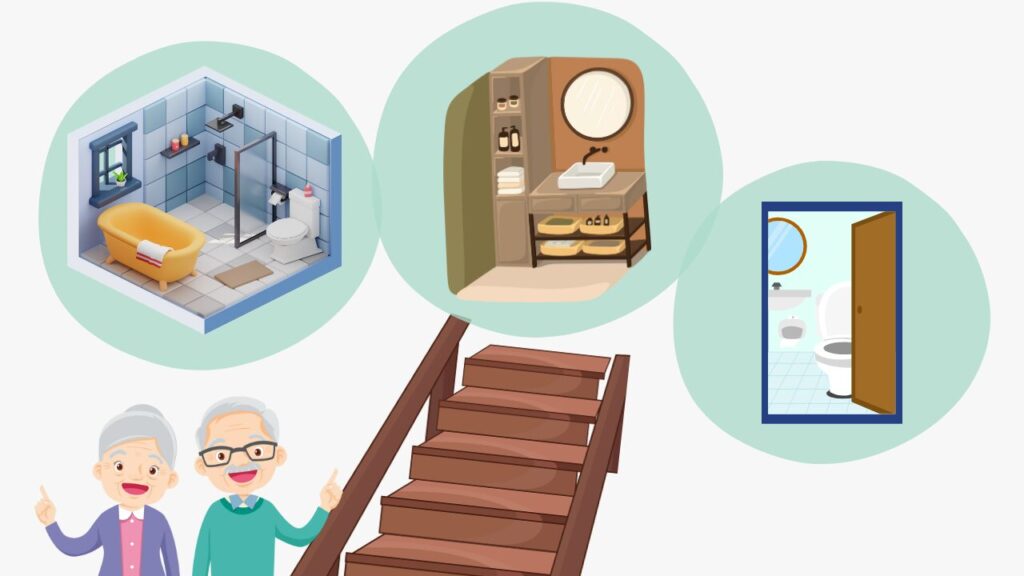
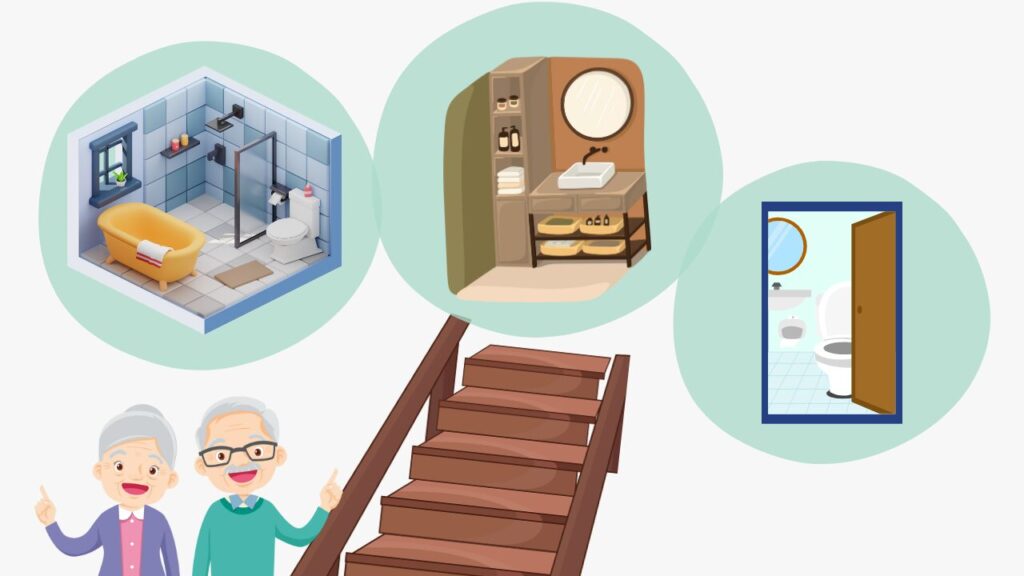
浴室やトイレ、洗面所などが2階にある住宅では、加齢や要介護状態になると「生活動線の確保」が大きな課題となります。
- 入浴や排泄のたびに階段を昇り降りする必要がある
- 夜間のトイレ移動時に転倒・転落のリスクが高い
- 住宅改修で手すりや滑り止めを設置する
- 介護認定を受けている方は、20万円以内の工事が1割~3割の自己負担で利用できる
- 運動習慣をつけて、筋力や体感バランスを鍛える
- 介護保険サービスをご利用の方は、デイケアや機能訓練特化型デイサービスなどを利用する
- 訪問リハビリで階段の昇り方、降り方の指導をうけるのも有効
- 賃貸の戸建ての場合は、元気なうちに住み替えを検討する
- バリアフリー、高齢者住宅への住み替え
水回りが2階にある戸建ての場合、階段の昇り降りができるかどうかは、毎日の生活に直結する問題です。
元気なうちから、運動習慣を身に着けておくことが、とても大切です。
- ラジオ体操をする
- ウォーキングをする
- ストレッチをする
ちょっとした運動を毎日続けることが、今の住居に長く住み続けられる、大きな備えです。
- 室内用の階段昇降機を設置する
- 階段の勾配や構造によっては、設置が難しい場合がある
- 1階だけで生活する方法を考える
- 寝室は1階に移動する
- ポータブルトイレを使用する(介護認定を受けている方は、10万円以内の商品を1割~3割の自己負担で購入できる)
- 入浴はデイサービスや訪問入浴を利用する
- 洗濯などの家事は家族に任せる、もしくは、訪問介護を利用する
- 施設入所を検討する
室内用の階段昇降機については、こちらを参考にしてみてください👉「ヤマシタ すぐきた」
階段昇降機の設置が難しい場合は、介護保険サービスを上手に活用するのがよいです。



ケアマネジャーや福祉用具の専門家に相談し、あなたに合う方法を見つけていきましょう。
まとめ


今回は、階段のある家に暮らす高齢者の方に向けて、住居タイプごとの備えや、階段昇降ができなくなった場合の対処法をご紹介しました。
住環境は高齢者にとって、在宅生活を継続できるかどうかの非常に大きな要素のひとつです。
- エレベーターのない2階以上の集合住宅
- 玄関まで5段以上の階段がある戸建て住宅
- 水回りが2階にある戸建て住宅
これら3つに共通する備えは、「運動習慣をつけて、筋力や体感バランスを鍛えておく」ことです。
「今は問題ない」と思っていても、加齢や体調変化は少しずつ進みます。
手すりの設置などで、転倒・転落のリスクをあらかじめ減らしておくことも大切です。
そうは言っても、病気や怪我などでやむを得ず、階段昇降ができなくなることもあるかもしれません。
階段昇降ができなくなった場合でも、ケアマネジャーや福祉用具の専門家に相談し、今の住居に住み続けられる方法がないか、可能性を探ってみましょう。
高齢になっても、できるだけ住み慣れた自宅で暮らしたい…そう願う方へ、この記事が少しでもお役に立てればうれしいです。