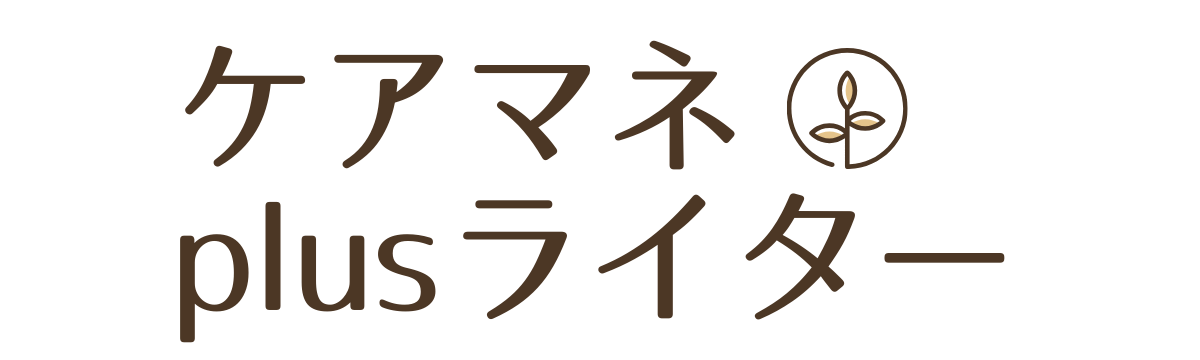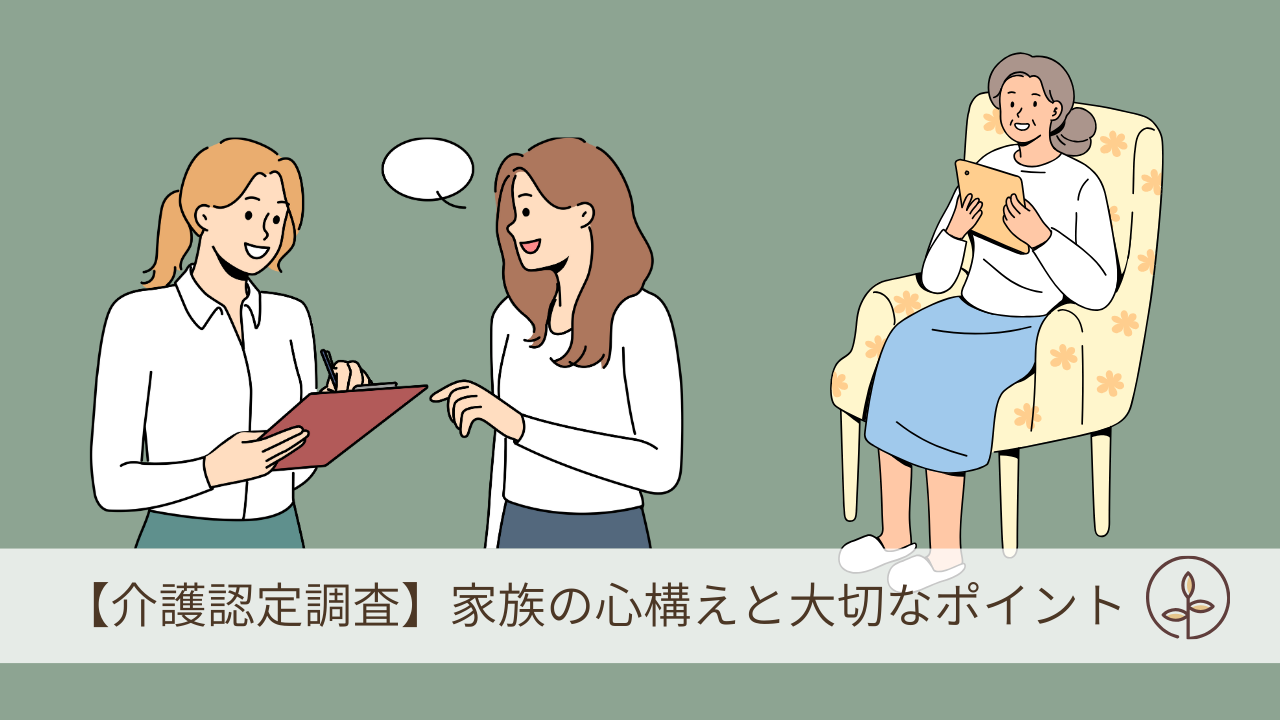介護保険サービスを利用する際に避けて通れないのが、介護認定調査(以下、認定調査)です。
認定調査を初めて受けるとき、ご家族としてはこのような不安や疑問を抱かれるのではないでしょうか。
- 家族は同席した方がいい?
- どんなことを聞かれるの?
- 事前に準備しておくことは?
私は主任ケアマネジャーとして、また、これまでに通算300件以上の調査を行ってきた現役の認定調査員として、ご家族のそうした気持ちをよく理解しています。
この記事では、あなたの不安を解消し、認定調査で「本当に必要な情報」をしっかりと伝えられるよう、ご家族が準備すべきこと、調査当日の心構え、そして結果に関わる大切なポイントを具体的に解説します。
介護認定は、これから始まる介護生活の第一歩です。
この記事を読んで、自信を持って認定調査に臨みましょう!
介護認定調査とは、介護度の審査に必要な聞き取り調査
認定調査とは、介護サービスを利用するための「介護度」を決める、大切な最初のステップです。
 認定調査員
認定調査員よくある質問にお答えします。
介護度は、認定調査票だけではなく、主治医が記載する主治医意見書も合わせて、介護認定審査会(要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成される合議体)で審議され、決定する仕組みとなっています。
認定調査前の心構えと準備
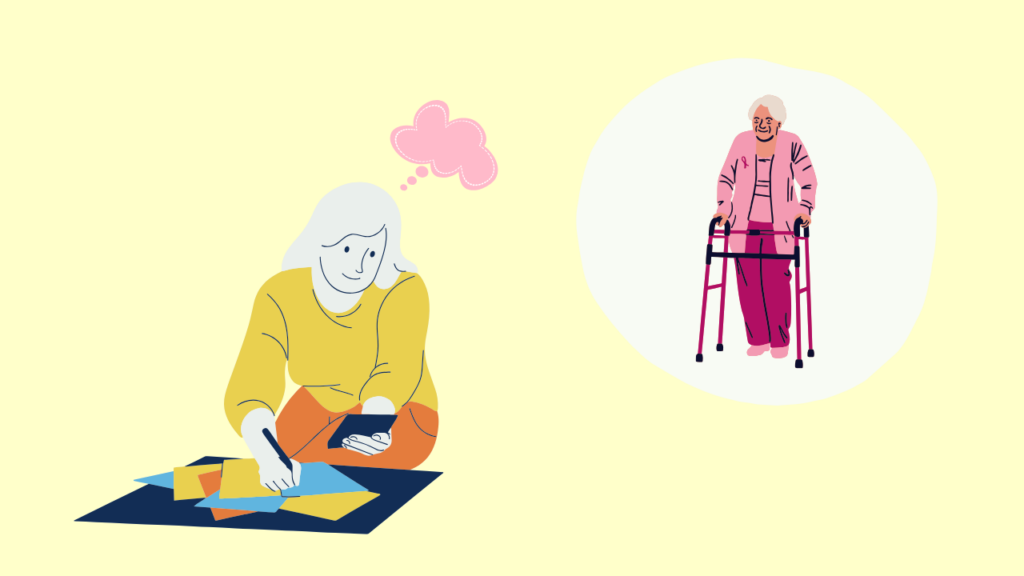
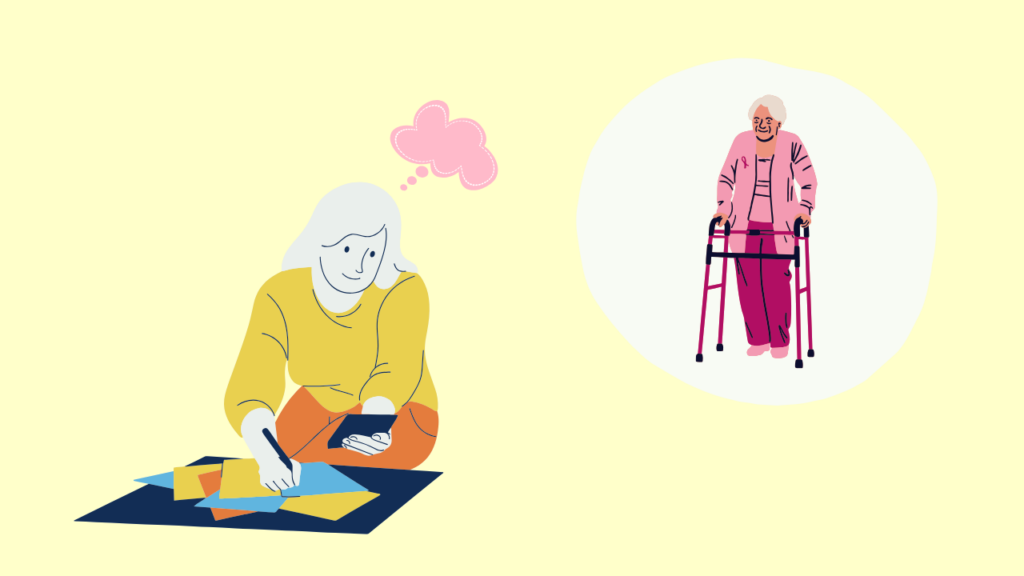
認定調査前の心構えと準備について、ポイントを解説します。
普段のありのままの様子を伝える準備をしておく
身体機能・起居動作の項目(寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行・片足立ちなど)では、ご本人に実際に行ってもらう、あるいはご家族から日頃の状況を聞いて、調査員がチェックをつけていきます。
普段はほとんどできないのに、初めて会った調査員の前では良いところを見せようと、たまたまできてしまうこともあるかもしれません。
「普段はできないこと」「介助が必要なこと」をリストアップしておくとよいです。
特に「大変だったエピソード」や「助けが必要だったこと」は具体的な情報になりますので、メモに控えておき、当日、調査員に伝えるようにしましょう。
精神・行動障害については「頻度」を把握をしておく
精神・行動障害【👉認定調査票(厚生労働省・参考資料)の4-1~4-15まで】の項目では、過去1か月間の状況について、下記のどれに該当するのか、調査員が聞き取りを行います。
- ない
- ときどきある:少なくとも1か月間に1回以上、1週間に1回未満の頻度で現れる
- ある:少なくとも1週間に1回以上の頻度で現れる
精神・行動障害がある場合には「頻度」がどのくらいなのか、把握しておくことが大切です。
精神・行動障害の聞き取りは、ご本人に聞きずらい内容ですし、ご家族もご本人の前では答えにくいことが多いのではないかと思います。
別室に移動する、調査員の帰り際に玄関先で話をするなど配慮が必要です。
あまり長い時間席を外すと、ご本人が不愉快に感じてしまう可能性もありますので、事前に頻度を把握しておき、調査員に伝えられるよう準備をしておきましょう。
認定調査当日の大切なポイント


ここでは、認定調査当日に押さえておく大切なポイントを3つ解説します。
正直に伝える
初めての認定調査で、ご本人ができないことを目の当たりにし、辛くなってしまうご家族もいるかもしれません。
認知機能の項目では、「毎日の日課」や「調査直前に何をしていたのか(短期記憶)」を調査員がご本人に質問します。
ご本人がなかなか答えられないもどかしさで、代わりに答えたり、ヒントを与えてしまうご家族の方が時々おられます。
実際よりできるように見せてしまうと、ご本人にとって適切な介護度が出ない可能性もありますので「良く見せよう」と思わず、「普段通り」を伝えることが大切です。
具体的に伝える
例えば、排泄に関する聞き取りで、ご本人がトイレで排泄できていたとしても、「声かけがないと間に合わない」「洗濯のときに下着が汚れている」などの状況がある場合には、具体的に調査員に伝えるとよいです。
「ない」「ある」のチェックだけではなく、調査員は聞き取った具体的な内容を特記事項に記載します。
具体的にこんなことがあった等のエピソードがあれば、調査員に状況が伝わりやすいです。
具体的なエピソードは、調査員が特記事項に記載してくれるでしょう。
ご本人の気持ちを尊重しつつ、家族が補足する
ご本人が「大丈夫です」「自分でできます」などと答えられても、調査員はご家族からの情報も重要視しています。
その場ではご本人の発言を否定せず、ご本人がいないところでご家族が補足するのがよいと思います。
認定調査でご本人が嫌な思いをしてしまうと、悪いイメージだけが残ってしまい、その後の介護保険サービス利用時の拒否に繋がってしまうかもしれません。
介護保険サービスを利用すると、ケアマネジャーやサービス事業者など、様々な人がご本人に関わるようになります。
認定調査はその第一歩です。
ご本人の気持ちを尊重しながら、認定調査を受けることを意識しておきましょう。
認定調査が終わったら
認定調査後、新しい介護保険証が届くまでの目安は約1か月です。
介護保険証に介護度が記載されているので、届き次第、確認するようにしましょう。
負担割合(1~3割)の範囲内で利用できる介護保険サービスの量は、介護度によって決められています。
介護度が決まると、介護保険サービスを使える量が明確になります。
認定結果に基づき、ご本人に必要な介護保険サービスを一緒に見つけ、計画を立てていくのが次のステップです。



信頼できるケアマネジャーに、是非ご相談ください。
まとめ
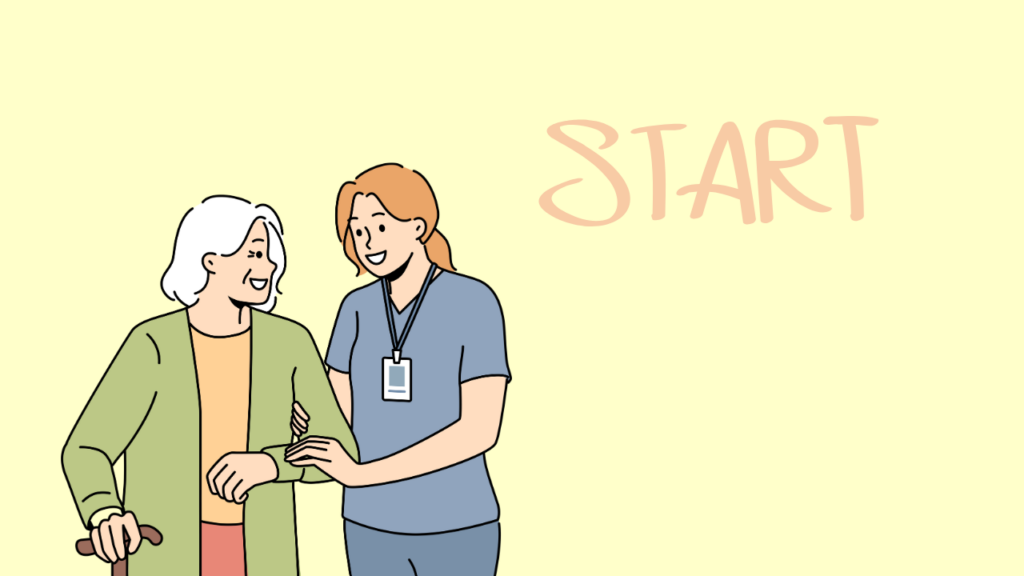
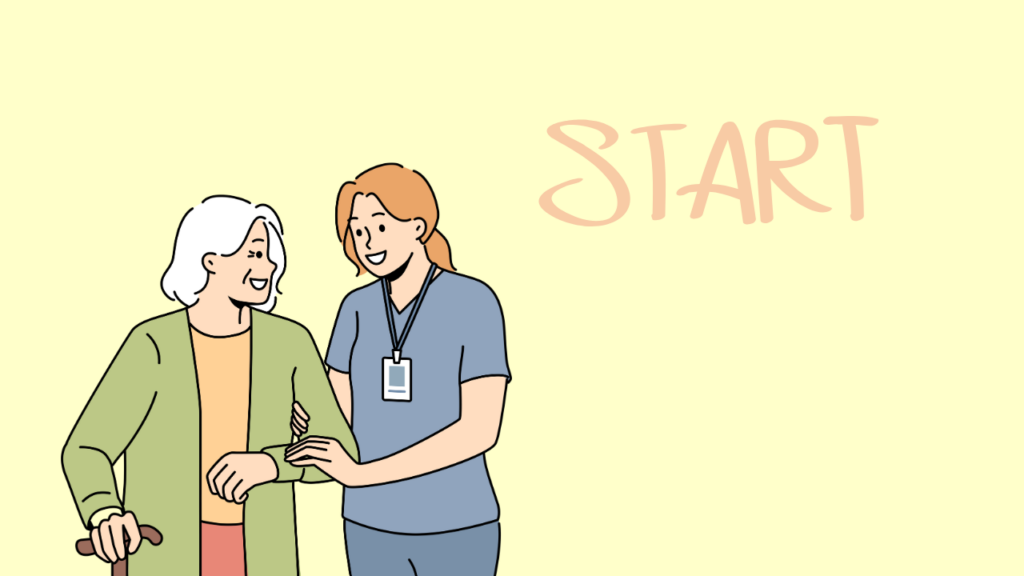
初めての認定調査は準備することが多く、不安を感じるかもしれません。
しかし、あらかじめ厚生労働省が示している実際の「認定調査票」を確認し、この記事でお伝えした「ありのままの様子を具体的に伝えること」「精神・行動障害については【頻度】を把握をしておく」ことで、落ち着いて当日を迎えられるはずです。
認定調査当日は、普段のありのままの様子を具体的に伝えることを心がけ、ご本人の気持ちを尊重しつつ、ご家族が補足で説明を行うようにしましょう。
認定調査は、決してご本人やご家族を「テスト」するものではありません。
これから始まる介護生活において、必要な介護保険サービスを過不足なく利用するための、大切なスタートラインです。
認定結果が出た後は、ケアマネジャーがご本人やご家族に寄り添い、最適な介護計画をたててくれるでしょう。
安心して一歩を踏み出してください。