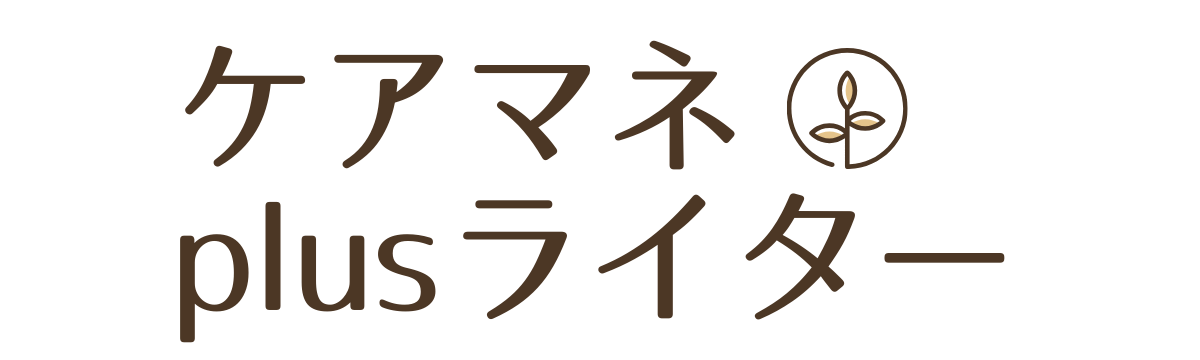「施設に入れるのはまだ早いかも…」
「できる限り自宅で過ごさせてあげたい」
「施設に入るとお金がかかるからどうしよう…」
そんな思いを抱えているご家族、多いのではないでしょうか?
特に、このような状況が重なると、家族としても「どうにかしなければ…」と焦ってしまうと思います。
- 転倒することが増えてきた
- 排泄の失敗が増えてきた
- 体調を崩すことが増えてきた
- 認知症により、日常生活のほとんどに手助けが必要
- 認知症による徘徊や他人への迷惑行為
- 家族の体調不良やストレスが限界
実は、このような状況になったとしても、介護保険には「自宅での暮らしを支える」ための、心強い在宅サービスが用意されています。
今回はその中から「定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)」「小規模多機能型居宅介護」の2つの在宅サービスを紹介します。
メリットだけではなく、現役のケアマネジャーだからこそ知っている、デメリットについても解説するので、自分の親に最適かどうか、この記事を参考に検討してみてくださいね。
1.定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)〜24時間、見守りと安心を届ける支援〜

定期巡回・随時対応型訪問介護(看護) どんなサービス?
1日に複数回、介護職員が自宅を訪問し、短時間のケア(安否確認、食事の声かけ、服薬、排泄介助など)を行います。
さらに、必要に応じて看護師の訪問や、緊急時の対応も可能。
緊急時の連絡は事業所が準備してくれるケア端末を使って行います。
ケア端末とは、電話回線を利用したボタン1つでオペレーターに連絡できる端末のことで、ペンダント型もあります。
介護職員が訪問したときに、1人暮らしや家族が不在で家の鍵が開けられない場合は、事前にキーボックスを設置しておくのが一般的です。
キーボックスとは、暗証番号を入力することで中に入っている鍵を取り出せる箱のことです。
玄関外の目のつきにくい配管などに取り付けておけば安心ですね。
一般的な訪問介護であれば、夜間や緊急時の対応は難しいのですが、定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)であれば、夜間も含めて緊急時も24時間365日対応できるのが最大の特徴です。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護) こんな方におすすめ
- 夜間の排泄介助や体位変換の介助が必要な方
- 排泄の失敗が多い方
- 歩行が不安定で転倒の多い方
- 認知症により、食事や服薬がきちんとできない方
- 1日に複数回の定期訪問と、もしものときの対応、両方確保したい方
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)のメリット
- 施設に入らなくても、24時間365日安心感のある在宅生活が可能
- その人に必要な短時間のケアが1日複数回受けられる
- 緊急時はオペレーターが対応し、必要に応じて訪問が行われる
- 家族が安心して自分の仕事に集中できたり、自分らしい生活がおくれる
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)のデメリット
- 要介護1~5が対象、要支援1・2は利用できない
- 要介護度に応じた利用限度額に占める割合が大きいため、他のサービス利用が制限される場合がある
- 利用料が月額のため、1日に支援を受ける回数が少ないと割高になる
- 介護職員は選べない、訪問時間も前後することがある
要介護度に応じた利用限度額に占める割合が大きいため、他のサービス利用が制限される場合がある
介護保険サービスは要介護度に応じて、1か月の利用限度額が定められています。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)は、手厚い24時間365日の対応をしてくれる代わりに、月額の利用単位数は他のサービスに比べて高くなります。
人によっては、「デイサービスに毎日行きたい」という方もいるかもしれません。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)を利用する場合、デイサービスの利用は多くても週に2~3回が限度と思っておいた方が良いでしょう。
ただし、自費(10割負担)でも良いという場合は、制限されることはありません。
利用料が月額制のため、1日に支援を受ける回数が少ないと割高になる
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)は1日に少なくとも2回以上の支援をしてもらうことで、利用料金に見合った内容になります。
例えば、1日1回、服薬支援だけで、緊急対応も必要ない場合には、通常の訪問介護の方が費用を抑えることができます。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)か、通常の訪問介護か、どちらが良いかは個々の状況によって違ってくるので、ケアマネジャーと相談するのが良いでしょう。
介護職員は選べない、訪問時間も前後することがある
介護業界の人手不足は深刻な状況となっていますが、定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)の事業所運営には、多くの介護職員が必要です。
最近では男性の介護職員もたくさん活躍されています。
24時間365日フル稼働している定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)は「あの人がいい」「女性じゃないとイヤ」などの介護職員に関する要望には、すべて応えることができません。
最初のうちは慣れないかもしれませんが、介護職員としっかりコミュニケーションをとりながら、どの介護職員が来ても大丈夫!になっていくのが理想的です。
介護職員は1日に何軒もの利用者宅をまわっているので、訪問先で予想外のアクシデントにあうことも多いです。
例えば、「訪問したら利用者が転倒していた」「熱があってしんどそう」「利用者が家にいない。どこに行った?」など。
介護職員が訪問してくれる時間は、あくまでも予定であって、遅れることもあると思っておきましょう。
自分の親にもアクシデントが起こる可能性はあります。
「お互いさま」という気持ちが大切です。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)を利用している事例
要介護4の1人暮らし。
歩くことはできませんが、食事は1人で食べることができます。
排泄は介護用ベッドの横に置いているポータブルトイレを使うか、もしくはオムツ。
ときどき、1人でポータブルトイレに移ろうとして転倒することがあります。
軽度の認知症はありますが、携帯電話を使うことはできます。
ケアマネジャーはこのようなサービス調整を行いました。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護
- 1日4回 朝・昼・夕・寝る前に訪問(着替え・食事・服薬・排泄介助・買い物など)
- デイサービス
- 週2回(入浴介助・社会交流)
- 訪問リハビリ
- 週1回(ポータブルトイレに移る訓練など)
- 福祉用具貸与
- 介護用ベッドなど
- 訪問診療・在宅薬局
- 月2回
- 配食サービス
- 毎日
定期巡回・随時対応型訪問介護の利用ができなければ、この方は施設入所を考えるしかありません。
1日4回の定期訪問に加え、転倒したときでも、随時対応してくれるサービスだからこそ、在宅での生活が維持できているのです。
このように定期巡回・随時対応型訪問介護は、在宅と施設の中間にあるような、心強い在宅サービスと言えるでしょう。
定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)について、もっとよく知りたい方は
👉「ハートページナビ」も参考にしてみてください!
小規模多機能型居宅介護 ~通い・訪問・泊まりを柔軟に組み合わせ~

小規模多機能型居宅介護 どんなサービス?
1つの事業所が、利用者やその家族の状況に応じて「通い(デイサービス)」「訪問(訪問介護員)」「泊まり(ショートステイ)」を柔軟に組み合わせて提供します。
1つの事業所で対応するので、介護職員とも顔なじみになり、利用者も安心して利用できます。
小規模多機能型居宅介護 こんな方におすすめ
- 「通い(デイサービス)」を中心い、時々「泊まり(ショートステイ)」も両方利用したい方
- 状況に応じて柔軟なサービスを受けたい方(例えば、体調不良で「通い」に行けない場合は「訪問」に切り替え)
- 認知症により、環境や人の変化が苦手な方
小規模多機能型居宅介護のメリット
- 「通い」「訪問」「泊まり」が同じ事業所で完結するため、利用者の混乱が少ない
- 家族の都合や介護負担に合わせて、使い方を柔軟に調整できる
- 家族が安心して自分の仕事に集中できたり、自分らしい生活がおくれる
小規模多機能型居宅介護のデメリット
- 居宅介護支援を利用中の方は小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーに変更になる
- 小規模多機能型居宅介護以外の介護保険サービスの利用が制限される
- 利用料が月額制のため、利用する回数が少ないと割高になる
- 対応エリアが狭い
小規模多機能型居宅介護以外の介護サービスの利用が制限される
小規模多機能型居宅介護と併用できる介護保険サービスは、「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「福祉用具貸与」「住宅改修」です。
これ以外は併用することができません。
すでに居宅介護支援のデイサービスや訪問介護を利用している場合には、利用を中止して、小規模多機能型居宅介護の「通い」や「訪問」に変更する必要があります。
利用料が月額制のため、利用する回数が少ないと割高になる
例えば、「通い」の利用が週1回だけで、「訪問」も「泊まり」も利用しない場合は月額制のため、かなり割高になります。
少ない回数であれば、居宅介護支援のデイサービスを利用するのが一般的です。
少なくとも週5日程度、「通い」もしくは「訪問」を利用するのが、料金に見合った内容となります。
小規模多機能型居宅介護か、居宅介護支援か、どちらが良いかは個々の状況によって違ってくるので、ケアマネジャーと相談するのが良いでしょう。
「通い」「泊まり」は1日に利用できる人数が決まっているため、希望通りにいかないことがある
小規模多機能型居宅介護は、利用定員が29名以下とされており、1日の「通い」や「泊まり」の利用定員も事業所ごとに決まっています。
他の利用者との兼ね合いで、この日は「通い」を希望したのに、定員がいっぱいで利用できないなんてことも…
ただし、「通い」で対応できなくても、「訪問」に切り替えて、利用者やその家族が困らないよう柔軟に支援してくれます。
対応エリアが狭い
小規模多機能型居宅介護の業務は「通い」の送迎、利用者宅への訪問、事業所に来られた利用者の食事や排泄、入浴介助など、非常に多忙です。
対応エリアは事業所にもよりますが、それほど広範囲ではありません。
事業所から自宅まで、車で10分~15分以内が目安となるでしょう。
小規模多機能型居宅介護を利用している事例
要介護2、子1人と同居。
子は平日就労しており、朝から夕方まで不在。
本人は認知症が進んでおり、食事をしたかどうかわからない。
入浴や着替えなども、声かけがないと難しい。
たまに1人で外に出て、道に迷ってしまうことがある。
小規模多機能型居宅のケアマネジャーは、このようなサービス調整を行いました。
- 「通い」週4日(昼食・夕食の提供、入浴介助、レクレーションの提供など)
- 「泊まり」1泊2日の週2日間(子の休息のため)
- 「訪問」週1日(昼と夕に訪問し、安否確認や食事の声かけなど)
- 福祉用具貸与(徘徊感知器のレンタル)
- 配食サービス 「通い」がない日の昼食・夕食
小規模多機能型居宅介護の利用ができなければ、同居の子は仕事をセーブしてキャリアを諦めたり、最悪の場合、介護離職となってしまう可能性もあります。
「泊まり」が利用できることで、同居している家族の負担はずいぶんと軽くなります。
利用者やその家族、一人ひとりのニーズに柔軟に対応してくれる小規模多機能型居宅介護は、心強い在宅サービスと言えるでしょう。
小規模多機能型居宅介護について、もっとよく知りたい方は
👉「ハートページナビ」も参考にしてみてください!
まとめ

今回は「定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)」「小規模多機能型居宅介護」の2つの在宅サービスを紹介しました。
どちらもデメリットはありますが、親が1人暮らし、あるいは同居の家族が仕事などで不在がちな家庭にとっては、非常にメリットが大きい心強い在宅サービスです。
私は、14年間、居宅介護支援でケアマネジャーをしています。
担当する利用者の方が、年齢とともに心身状態が悪くなったり、家族が介護で疲弊するケースをたくさん見てきました。
「まだ自宅で過ごしたい」という利用者の想い、「まだ自宅で過ごさせてあげたい」という家族の想いをかなえるために、一人ひとりの状況に応じて「定期巡回・随時対応型訪問介護(看護)」「小規模多機能型居宅介護」の利用を提案しています。
小規模多機能型居宅介護を希望された場合、小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーに引き継ぐことになるので、少し淋しい気持ちにはなりますが、それでも「いってらっしゃい!」という気持ちで送り出しています。
利用者とその家族が元気に過ごせるのがなによりです。
※自治体や事業所により、ここで説明した内容と異なる場合があります。詳細に関しては、必ずケアマネジャーや事業所に問い合わせてくださいね。