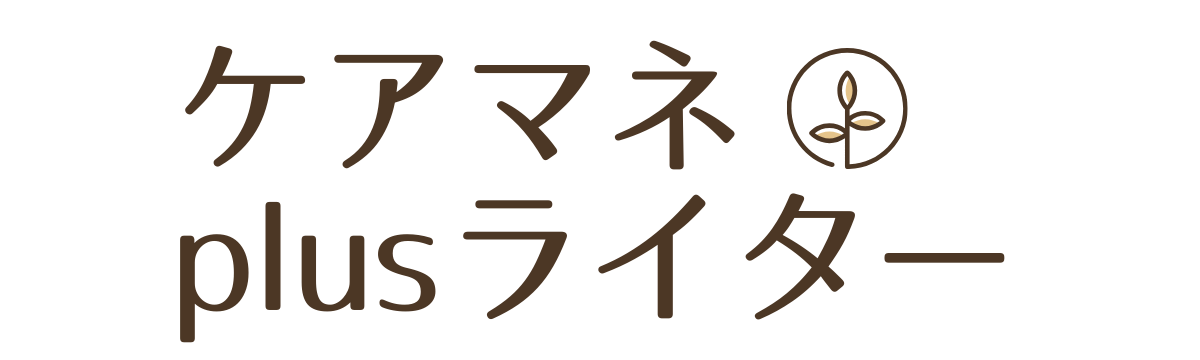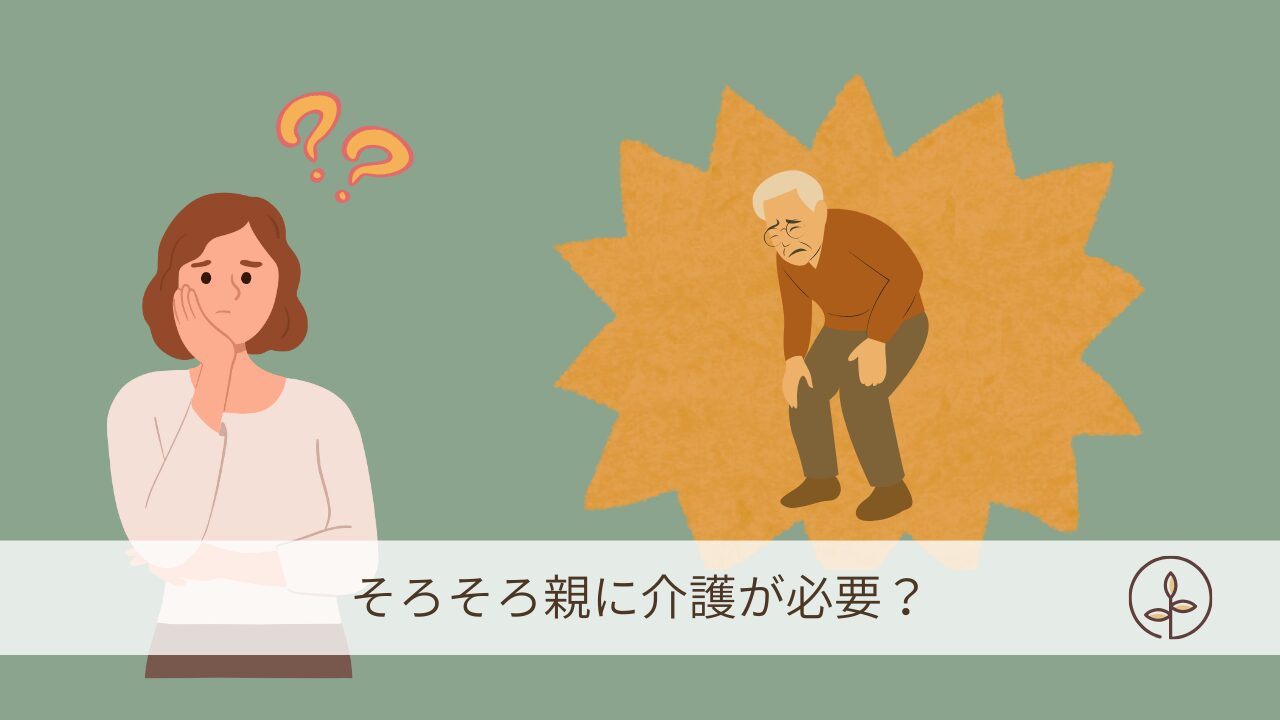「親が倒れた」
「最近なんだか様子がおかしい」
「このまま一人暮らしで大丈夫?」
初めて親に介護が必要?と感じたとき、多くの方は「どうすればよいのかわからない」と戸惑ってしまうと思います。
今回は居宅介護支援事業所で主任ケアマネジャーをしている私が、最初に何をするべきかについて、現場の目線を含め、わかりやすく解説します。
まずは、「現実を整理」しましょう

まずは、落ち着いて親御さんの現在の状況を確認します。
- 身体の状態(歩けるか・転倒が増えているか)
- 認知機能の状態(物忘れ・会話の内容に違和感がないか)
- 生活の様子(掃除・食事・買い物などに支障がでていないか)
- 親本人の希望(施設に入りたい・家で暮らしたい)
「なんとなく不安」から「何が心配か」整理していくことが第一歩です。
家族で話し合う時間をもちましょう
介護は一人で抱えるものではありません。
早めに家族間で話し合い、以下のような点を確認しておきましょう。
- 介護をする人は誰か(みんなでどう分担するか)
- 介護費用の負担はどうするのか
- 仕事と介護の両立について
- 将来、施設への入所を考えるのか
一人で全部を背負い込む前に、しっかり家族間で共有しておくことが大切です。
医療機関に相談しましょう
親御さんにかかりつけの病院があるときは、医師に相談してみましょう。
例えば、親御さんの物忘れが気になるのであれば、かかりつけ医が整形外科や泌尿器科など、専門医でなかったとしても、まずは相談することが大切です。
必要に応じて、総合病院であれば専門の診療科、個人病院であれば他の病院を紹介してくれます。
診断や今後の見通しについて、専門的な意見を聞いておくことはとても大切なことです。
その際、医師に「介護保険を申請したい」と伝えておくと、介護認定に必要な主治医意見書の記載について、医師が心づもりしておいてくれるでしょう。
地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に連絡しましょう
「誰に相談したらいいかわからない…」という方は、まずは地域包括支援センターへ連絡しましょう。
地域包括支援センターは公的な相談窓口で介護の総合相談を無料で行っています。
親御さんが住んでいる地域の地域包括支援センターを調べて相談しましょう。
ケアマネジャーが在籍している居宅介護支援事業所でも相談にのってくれます。
ハートページナビを活用すれば簡単にお近くの居宅介護支援事業所を検索することができます。
👉ハートページナビは全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌
介護保険を申請しましょう
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所では介護保険の申請を代行することができます。
自分で行いたい場合は市区町村の介護保険の窓口でも行うことが可能です。
これによって、介護保険サービス(訪問介護や訪問看護、デイサービスなど)を利用するための準備が整います。
介護認定が出るまでは約1か月かかりますので、早めに申請を行うようにしましょう。
要介護認定(要支援1・2・要介護1~5)によって、使える介護保険サービスの量が決まります。
順に、要支援1→要支援2→要介護1→要介護2…→要介護5
要介護5が一番介護度が高く、介護保険サービスを使える量も多いです。
介護保険サービスを使える量とは、1割~3割の自己負担で使える量を指します。
1年ごとに親御さんの所得に応じて自己負担の割合が決めらる仕組みになっています。
介護保険を申請すると「介護保険負担割合証」が市区町村より発行されるので、親御さんの負担割合を確認しておくようにしましょう。
ケアマネジャーと一緒に「ケアプラン」を作成
要介護認定(要支援・要介護1~5)の結果が出た方には、担当のケアマネジャーがつきます。
親御さんご本人やご家族の心配事・困っていることなどをケアマネジャーが聞き取り、必要と思われる介護保険サービスを提案してくれるでしょう。
利用したい介護保険サービスが決まったら、ケアマネジャーがサービス事業所と調整を行い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
介護サービス計画(ケアプラン)とは、簡単に言うと介護保険サービスを利用するために必要な計画書です。
これらのケアマネジャーの支援については、自己負担はありません(※2025年現在)
必要な介護保険サービスを少しずつ利用しましょう
「いきなり全部をやろう」としなくても大丈夫。
最初は、例えば週1回のデイサービスや家事支援などの訪問介護など、必要最小限から始めてみましょう。
サービスを受ける前にサービス事業所の担当者と話し合いをもつ場をケアマネジャーが作ってくれます。
これを「サービス担当者会議」と言います。
「サービス担当者会議」にはご本人・ご家族(参加可能な場合)・ケアマネジャー・サービス事業所の担当者が参加します。
サービス担当者会議ではケアマネジャーが作成した介護サービス計画(ケアプラン)について、参加者で確認し、必要であれば介護サービス計画(ケアプラン)の修正をケアマネジャーが行います。
サービス事業所がどんな内容の支援をしてくれるのか?介護サービス計画(ケアプラン)にはそれが記載されているので、しっかりと確認しておきましょう。
ご本人もご家族も、無理なく慣れていくことがポイントです。
制度や支援を活用しましょう
介護保険以外にも、以下のような制度や支援があります。
- 介護休業制度
- 高額介護サービス費の支給
- 成年後見生徒(認知量による金銭管理のサポートなど)
- 民間の介護サービス
仕事と介護が両立できるよう、使える制度を知っておくことが大切です。
高額介護サービス費の支給はお住まいの市区町村窓口へ。
成年後見制度や民間の介護サービスなどはケアマネジャーに相談するのがよいでしょう。
介護する側のケアも忘れずに
介護は長期戦になることも多いです。
「自分の身体と心の健康」も大切にしてください。
- 相談できる人をもつ
- 生き抜きの時間をつくる
- 必要なときは支援サービスを積極的に使う
無理をしないことが、親御さんにとっても良い介護につながります。
まとめ

親の介護が始まると、不安や戸惑いはつきものです。
一人で抱え込まず、まずは相談することから始めてみてください。
初めてのことは一度にたくさん教えてもらっても覚えきれないものです。
まずはひとつずつ、担当のケアマネジャーに相談しながら不安を解消していきましょう。