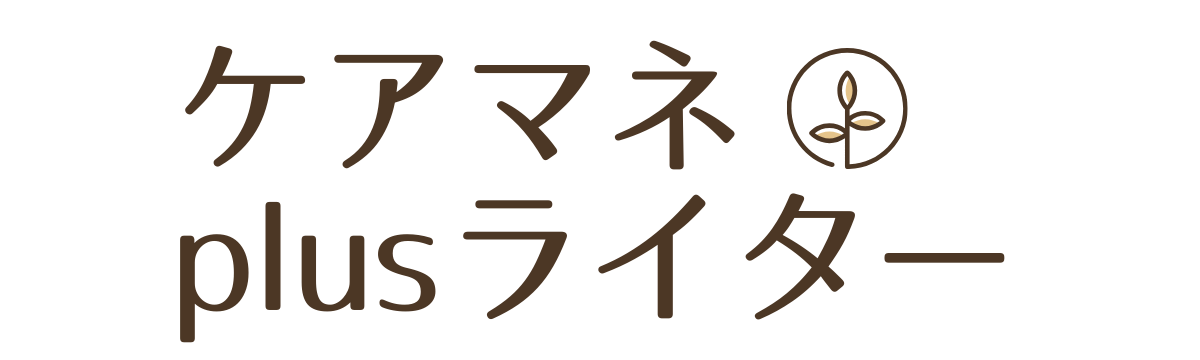- 特別養護老人ホームに入ると、どんな生活になるんだろう?
- 1日の流れや外出は自由にできるの?
- 個室と多床室の違いは?
特別養護老人ホーム(以下、特養)の入所を検討しているご本人やご家族にとって、特養での暮らしは気になることがたくさんあります。
筆者は従来型特養(多床室)に2年間、ユニット型特養(個室)に2年間の勤務経験があり、現在は居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして、ご利用者の特養への申請をサポートしています。
この記事では、私のこれまでの経験をもとに
- 特養での1日の過ごし方やイベント
- 居室の種類
- 注意しておきたい制度のポイント
について、わかりやすく解説します。
特別養護老人ホームとは
特養は、要介護3以上の方が対象となる公的な介護施設です。
要介護1・2の方でも特例的に入所できる場合がありますが、非常に稀です。
長期的な入所を前提としており、介護職員や看護職員による日常生活の支援や医療的ケアを受けながら生活します。
- 原則として「終の棲家」としての長期入所が可能
- 所得に応じて利用料が軽減される仕組みがある
- 介護度が高い方でも安心して生活できる体制が整っている
特養の1日のスケージュール(例)

施設によって細かな違いはありますが、多くの特養では以下のようなスケージュールで生活しています。
排泄や着替え・整容の介助、バイタルチェックなど
朝食後に服薬や口腔ケア、排泄介助など
入浴(交代制)、生活リハビリ(洗濯物たたみなどのお手伝い)、塗り絵などの余暇活動、レクリエーション、ベッドで休む、家族の面会など
昼食後に服薬や口腔ケア、排泄介助など
入浴(交代制)、生活リハビリ(洗濯物たたみなどのお手伝い)、塗り絵などの余暇活動、レクリエーション、ベッドで休む、家族の面会など
時々、職員と一緒におやつを手作りして楽しむことも…
夕食後に服薬や口腔ケア、排泄介助など
順次、着替えを済ませ、就寝
入浴は週2回が一般的で、交代制で時間が割り当てられています。
レクリエーションは体操、歌、脳トレなど、施設ごとに工夫が凝らされています。
 筆者
筆者私が勤めていた特養では、喫茶コーナーがあり、ボランティアの方が美味しいコーヒーを入居者に提供されていました。
コーヒーを飲みながらボランティアさんとお喋りするのを楽しみにされている方も多かったです。
特養の年間のイベントや行事
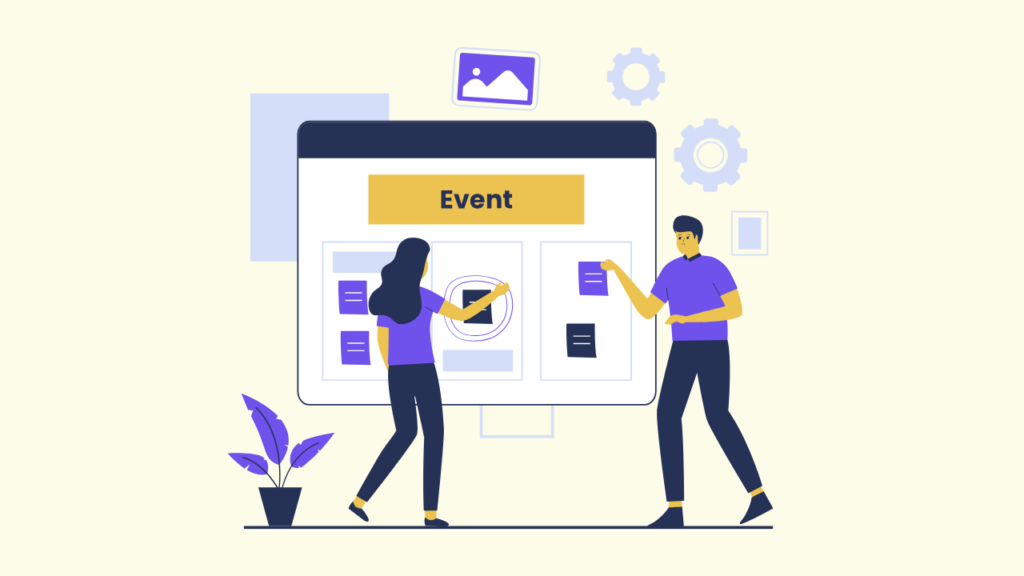
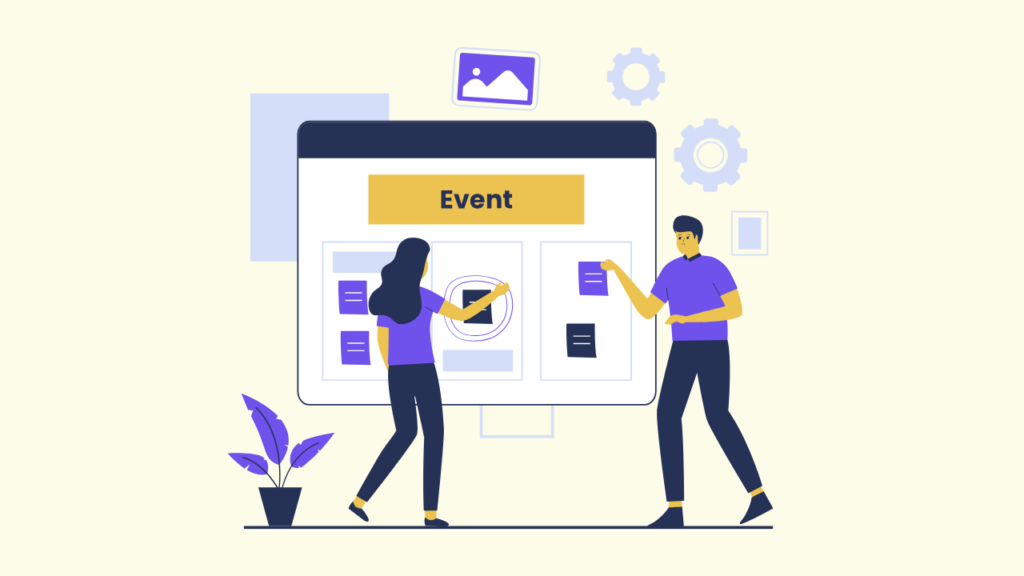
特養では、入居者が楽しみを持って生活できるよう、季節ごとのイベントを積極的に行っています。
<特養で行われるイベントの例>
| 春 | お花見・端午の節句・母の日など |
|---|---|
| 夏 | 父の日・七夕・花火大会・納涼祭など |
| 秋 | 敬老会、紅葉狩り、ハロウィンなど |
| 冬 | クリスマス会・餅つき・新年会・初詣・節分など |
地域のボランティアや近隣の保育園や学校との交流会が行われることもあります。
誕生日会などの個別行事も大切にしている施設も多く、生活にメリハリをつける工夫がされています。



私が勤務していた特養では、「ドッグセラピー」がありました。過去に犬を飼っておられた入居者の方は大変喜ばれていました。
可愛いワンちゃんに、心が癒されます。
特養入所中の外出・外泊について
「施設に入ったら外に出られないのでは?」と心配される方もいますが、外出や外泊は可能です。
- 家族との外食や買い物など、日帰り外出
- 数日間の外泊(自宅や家族宅など)
- 通院や法事などの一時外出
外出・外泊の際は、事前に施設へ連絡し、体調確認や薬の管理などを行います。
また、施設によっては感染症対策や安全管理のため、制限が設けられる場合もありますので、事前確認が必要です。
特養の個室と多床室の違い
特養には「個室」と「多床室(4人部屋など)」があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、希望や費用負担に応じて選択します。
| 項目 | 個室 | 多床室 |
|---|---|---|
| プライバシー | 高い(自室で過ごせる) | 低い(仕切りはあるが共有空間) |
| 料金 | 高め(居住費が上乗せされる) | 安め |
| 人との関わり | 少なめ(自分のペースで生活) | 他者との交流が生まれやすい |
| 環境 | 静かで落ち着ける | 賑やか・共同生活の雰囲気 |
現在はユニット型個室の普及が進んでおり、「1ユニット=10人前後」で、家庭的な雰囲気の中で生活する形も増えています。



ユニット型特養では居室に使い慣れた家具や仏壇などを持ち込み、落ち着ける環境を作っておられる方が多くいます。
【特養】注意しておきたい制度上のポイント
特養は「終の棲家」として長期入所できる施設ですが、いくつか注意しておきたいルールがあります。
3ヵ月以上の入院が続くと退所になる場合がある
長期入院で居室を空けたままになると、施設によっては退所扱いになることがあります。
その際は、退院後に再入所できる保証がないこともあるため注意が必要です。
入院が長引きそうな場合は、施設の生活相談員や入院先の医療ソーシャルワーカーに相談することが大切です。
医療的ケアは内容によって対応できないことも
経管栄養・夜間の痰吸引・インスリン注射・透析などの医療的ケアが必要な場合、施設側の体制によっては、受け入れ可否が分かれます。
医療的ケアが必要になった場合、介護医療院への転所や療養型病院などへの入院を検討するケースもあります。
施設の生活相談員とよく話し合うことが大切です。
介護保険の更新で要介護2以下になると退所の対象に
特養の入所条件は「原則、要介護3以上」。
介護保険の更新で要介護2以下になると、退所を求められることがあります。
ただし、やむを得ない事情がある場合は継続入所が認められるケースもあります。
その他、特養入所前に知っておきたいこと
利用料金について
利用料は「介護サービス費+居住費+食費+日常生活費」で構成されます。
所得に応じた負担限度額認定を受けることで、低所得の方でも安心して利用できる仕組みがあります。
面会時間や差し入れのルール
面会時間や差し入れの可否、持ち込み品の制限などは施設ごとに異なります。
感染症が流行っている場合などは、予約制やリモート面会を取り入れている施設も増えています。
入所までの待機期間
特養は人気が高く、待機者が多い地域では入所まで数カ月~1年以上かかることも珍しくありません。
申し込み順ではなく、緊急性や在宅困難度によって優先順位が決まります。
特養に限定するのであれば、複数の施設に申し込みをした方がよいでしょう。
まとめ


- 特養は要介護3以上が対象で、長期入所が可能
- 1日のスケージュールは生活リズムを大切にしている
- 外出・外泊も可能で、季節行事も充実
- 個室・多床室には費用や過ごし方に違いがある
- 医療的ケアや介護度の変化など、制度上の注意点もある
施設によって雰囲気やサービス内容、対応の範囲は大きく異なります。
見学やパンフレット請求を通じて、ご本人に合った施設を見極めることが大切です。
元特養勤務、現在はケアマネジャーの筆者より、ひとこと
「特養=病院のような生活」と思われがちですが、実際は家庭的な雰囲気で穏やかに過ごされている方が多いです。



私が以前勤務していたユニット型特養は、個別性を大切にしている素晴らしい施設でした。
ある人は喫茶コーナーに行き、ある人は居室でテレビを見て過ごし、ある人はリビングで職員とお喋りを楽しむ…居室もその人それぞれの個性があり、「自分もこういうところに入りたい」と思える施設。
特養の申し込みを検討される方は、見学や担当のケアマネジャーに施設の評判を聞いてみるなどして、「終の棲家」となる施設を選んでくださいね。